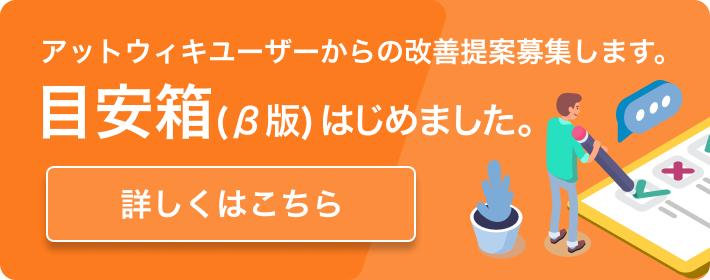「暁王と剣姫第三章」(2008/01/31 (木) 22:22:52) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*第三章 秋望城合戦
「暁王、そなたらの力見せてもらおう」
すでにこの城は包囲されていたが、曙乃王の態度には余裕があった。たしかに落ちかけているが、間者の情報によれば文月の戦力のほとんどはこの城を落とすのに使われているらしい。つまり、逆にこの場を凌いでしまえば大きなチャンスが生まれるとも言えよう。
だが既に城には火の手が上がっていた。文月の剣と王達は既にこの秋望城に攻城戦を仕掛けている。つまり落城寸前、絶体絶命である。
曙乃王は窓の外を見やった。
眼下に広がるは外に見える文月の一団。その中心には見知った顔-あの糸目の男も居る。
秋望城とは暁の地、学園の内部にある葉月と文月の境界、秋立平原を一望する葉月の最前線の城である。今日この日に曙乃王と暁王が会談すると言うことは極秘であるハズであった。
どこから漏れたのだろうか、外に繰り広げられる惨状に眉を顰めながらも、他人事のように考える。
「お館様!お逃げくださ……ぐぁ」
急に扉が開け放たれて曙乃王付きの王の一人が転がり込んできた。その王は言葉を言い終わるよりも先に射貫かれてそのまま壁に繋ぎ止められる。
そして数組の王と剣がなだれ込んできた。天守にあった和室は踏み荒らされ、四人を取り囲むように包囲網を作る。
曙乃王は伝令に来た配下の死を悼むように目を伏せると暁王と背中合わせに立ち、死角をを減らす。
「油断するな!一斉に掛かれ!」
そして、号令は下った。統率のとれた動き、よく訓練されている剣と王だ。
「暁王、よいな?」
「ええ」
暁王は問いかけに対し背中越しに頷くと、剣姫に目配せをした。
それはまるでスイッチが入ったようであった。畳の上を風が駆け抜ける。
一太刀目、地を這うような大きな踏み込みで大輪の花が咲く。吹き上がる血飛沫を凍り付かせ盾とする。その盾で次に襲いかかろうとしていた剣の踏み込みが甘くなる。一瞬で十分だ。その踏み出しの遅れは剣姫には十分な隙に見える。
二太刀目、その刀は神速の域に達する。前掛かりになった身体をその間に立て直し、振り下ろされる剣を避けると同時に腕を切り裂いた。二人目。
三人目から繰り出されたのは時間差による炎の風であった。剣姫は伊達に滅龍騎士を長くやっていない。これは何なく切り裂いて霧散させる。そして次の一太刀で叩き伏せた。
「剣姫、後ろ!」
暁王は剣姫の後ろから来た剣の一撃を腰の刀で受け止め、後ろに下がる衝撃で剣姫と体を入れ替える。二、三歩よろめくが、そのまま立ち止まった。その間に剣姫はその剣を切り伏せる。
暁王が振り向くと曙乃王とその剣、御影の周囲には誰一人として立っては居なかった。
息一つ乱れていない。少々乱れたスカートの裾を直してはいるがその所作は見まがう事なき王であった。
下から第二陣がおしよせる音が聞こえる。
「曙乃王、このままでは、埒があきません」
暁王が真剣な眼で訴える。
「案ずるな、暁王。この部屋には仕掛けがあってな」
曙乃王は悪戯っぽく笑うと御影に床の間の軸を外させる。『かちり』と二重に音がした。渇いた音の方を見ると側面に先ほどまではなかった穴がポッカリと空いていた。
そして、四人は頷くと中へ飛び込んだ。
「なぜだ、何故未だ首級を上げたという報告がない!」
3度目の見失ったと言う報告を受けた鋼牙の王は激高していた。力任せに報告した使者を足蹴にする。情けない悲鳴を上げながら伝令は地面を転がる。
「伝令に八つ当たりしても、何もでませんよ」
それにひきかえ糸目の男は至って冷静であった。その眼は軽率な部下を見咎めるものである。
数瞬の沈黙。文月の陣に緊張が走った。
「鋼牙!」
傍に佇んでいた巨漢が前に出る。
「私が自ら出る、陽炎殿、貴公はここで高みの見物でもして居るのだな!」
糸目の男、陽炎と呼ばれた王はその後ろ姿が消えるのを見届けると口の端を微妙に釣り上げたが、すぐにその笑みも消し部下に指示を出し始めた。
暗闇を4人は走る。
自らの配下の者を見捨てるわけではない。ただ、この状況を打開するためだけに4人は走っていた。いったいどれくらい走ったのだろう。
暁王はその先に光を見た。生命力にあふれた鮮烈な夏の緑と熱い風。そして戦列を見下ろせる位置。
そこには葉月の誇る精鋭部隊が集結していた。
「時は今、といこうかの、暁王」
曙乃王の手が振り下ろされる。
先陣を切って突撃したのは鎧姿の男であった。その一撃は山をも砕きかねないものだ。それに並走して小柄な蛇剣の少女が陣を切り裂く。そのあとを守るように一組の男女が手本のような戦闘を繰り広げていた。
その部隊が止まったのは倍以上の数にものぼる剣と王がいたからだ。それはすなわち決戦の舞台にたどり着いたことを意味していた。
「曙乃王、暁王、行ってください!」
精鋭部隊のメンバーが口々に言い出す。鈴を付けた少年が、黒衣の青年が、剣であろうと王であろうと関係なく曙乃王を信じているのである。この状況を打破できるのは彼女であることを。
そんな曙乃王を暁王は羨ましく思いながらも前に歩を進める。
「やっと見つけたぞ!」
鋼牙の王の声が本陣前に響いた。
「あれは……あの時の……」
曙乃王が剣姫の言葉を手で制する。
「お主たちは前に進むがいい。この場は我らに任せておけ」
駆け抜けようとする暁王に鋼牙の剣が振り下ろされようとするが、御影が割って入る。
「ここはお願いします。また、会いましょう」
暁王は後ろを一瞥すると剣姫とともに駆けだした。
「あ、ちょっとまて、逃げるな!」
その声は無視して前に進む。
本陣にたどり着くと、糸目の男が悠然と待ち構えていた。
「ほう、曙乃王ではなく、お主らが来るとはな。剣姫とその王。噂は聞いている」
静かな口調で言葉を紡ぐ男。
「文月としては睦月と葉月が組む、これは喜ばしいことではない。それはわかるな?」
その糸目の男、榊王はすらりとした刀身を抜きはなつ。
「ええ、榊王」
暁王はそのプレッシャーに耐えつつも笑みを浮かべている。
「前口上は、それで十分だ、我は陽炎の王、榊、いざ尋常に!」
「我が名は剣姫、我が王、我が君のためにいざ参る!」
ここに決戦の火ぶたは切って落とされた。
先に手を出したのは陽炎であった。陽炎の獲物は斬馬刀、野太刀と呼ばれる長大な刀である。当然その長さゆえに相当の重量を持ち、馬ですら一撃で切り倒すそんな武器であった。もちろんその重さから使い手は相当限られており、昔の世においてはこの武器をを扱えることは一種のステータスであった時代もあったという。
滅龍騎士が出現するようになり超大剣がよく見られるようになってからはその風潮も収まったが、長大な太刀を振り回し、扱うことができる剣士はやはり一目置かれるのは当然といえよう。
「シャァッ!」
陽炎は唸り声をあげつつ逆袈裟に切り上げる。その延長上にいるのは、剣姫。
捉えたと思った瞬間に視界から剣姫の姿は消えていた。当たる直前に高く飛び上がっていたのだ。空振ってガラ空きの上体に飛びこみながら切りつける。
完全に捉えたとその一撃は陽炎の姿を両断する。
……が、手ごたえがない。剣姫はもう一度剣を振うが同じように届いたと思った斬撃はただ虚しく宙を切るだけであった。
次第に陽炎の野太刀が剣姫の体を掠めるようになってきだした。当てても当てても手ごたえのない相手に、剣姫の中の焦りの心が加速度的に増す。それはまるで雪のようにうずたかく積もっていく。
そして、致命的な一撃が今まさに振り下ろされん時に剣姫には聞こえた。
「大丈夫、剣姫」
焦る心を暁王の声が溶かしていく。振り下ろされる刃がゆっくりと見えた。
その一撃は髪の一房を巻き込んだものの剣姫に届くことはなかった。
「睦月とはすべての始まりの一節なり。我は行使する。剣姫の名に於いて来たれ氷嵐」
「文月は炎夏の先駆けの一節なり。我は行使する。陽炎の名に於いて来たれ炎風」
世界が白と赤に塗り分けられる。剣姫から放たれる冷気は周囲の物を凍てつかせていく。その一方炎風に晒された草木は渇き、焼け落ちる。それは絶対たる炎と氷雪の競演であった。
剣姫は白き衣を身に纏いながら炎風の中を駆け抜けだした。その一撃は神速の一撃。少しでもスピードをゆるめれば白い衣としてまとった冷気は消滅し、炎風に晒されるだろう。 だがしかし、暁王の声を受けた剣姫には微塵の迷いも見られなかった。
一閃。
陽炎はとっさにその剣姫の一撃を野太刀で受け止めた。高熱と超低温に一気に晒されたそれは完全に折れる。陽炎はその一撃を受けて、王を巻き込みつつ氷嵐の中へと巻き込まれていく。
かくして、文月との合戦は決した。後に秋望城合戦と呼ばれるこの戦は文月の退却という形で終結したが、葉月・睦月両国にも大きな爪跡を残すこととなる。
大将を打ち取られた軍は抵抗を続けてはいたが、次第に抵抗を弱めていき、後に、本国が落ちるに至る原因となった。
歴史にはこう記されている。
これ以後、葉月・睦月の両雄は暁を二分するための戦いに身を投じることになる、と。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: