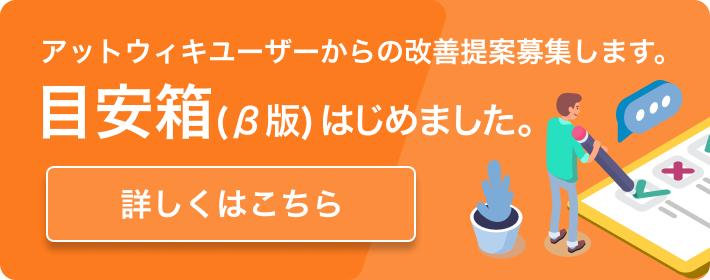「ジャーナリストの誤謬」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「ジャーナリストの誤謬」(2007/12/06 (木) 09:30:54) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
ジャーナリストの誤謬
- 東谷暁「エコノミストは信用できるか」を検討する -
本文章の文責は英-Ranにあります。ご意見、ご感想、ご批判などはarn@cafe.email.ne.jpまでお願いします。本文章は著作権や出所が明示される限りにおいて、自由に配布して頂いてかまいません。
はじめに
東谷暁というジャーナリストが書いた「エコノミストは信用できるか」という本がある。この本は、誤解に基づくインフレ目標批判をしていることもあって、真っ当な経済学徒の評判は極めてよろしくない。しかし私の読んだ限りでは、この本は紛れもなく良書である。各種経済論理をまとめあげ整理したその手腕、努力は間違いなく賞賛に値する。
本書の特徴はエコノミストの主張の一貫性を頼りに「エコノミストの格付け」を行う点にある。数多くのエコノミストの言論を記録し、その変遷を調査することによって不誠実なエコノミストをあぶり出すという行為は確かに重要である。日本最大の経済紙、日経新聞のいい加減さを白日の下に晒した点などを考えれば、著者の東谷氏は画期的な仕事をしたのではないかとさえ思える。言論の自由は「目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない」という効果が現れるからこそ意味がある。学問の歴史が論争の歴史であることからもわかるように、本書のようなフィードバックがあってはじめて正しい言論が保たれるのだ。
また、本書では多くの部分を「金融政策」あるいは「インフレ目標論」に割いている。リフレ派にとっては当たり前のことのように思えるが、これは画期的なことである。現在の「世間知」を作り出している新聞、あるいはテレビといったマスコミを言論の中心として見た場合、その論点は「構造改革 VS 財政政策」であって決して「構造改革 VS インフレ目標」ではない。インフレ目標論は読売新聞が全面的に押し出しているはいるものの、未だに中心的論説にはなりえていない。
しかし、著者の東谷氏は十年にもわたりエコノミストの言説を追う中で、「インフレ目標」が大きな争点のひとつになっていることをきちんと見抜いている。それだけではなく、良いデフレ論への批判や「『構造改革』という言葉で指摘されるものが、いったい何を意味していたのか」など鋭い指摘も多い。たとえ、経済学の知識がなくともきちんと調べさえすれば適切な議論に近づくことができるのである。
だが、これほど入念な調査を行ったにも関わらず、本書の出した結論や指摘を「正しさ」という基準で見た場合、多くの誤りを含むのも事実である。なぜ正しくないのか。なぜ正しい結論に辿りつけないのか。ここでは、本書の内容に批判・検討・補足を加えながら、その問題点を明らかにしたい。
エコノミストは「主張の一貫性」で評価されるべきか
本書において、著者は「主張の一貫性」という基準に基づきエコノミストに対して評価するとしている。確かに一見、この主張は正しそうに見える。通常、時と場合によって言論をころころと変える人は不誠実と見なされる。エコノミストが経済の専門家であるなら唯一確実な真実を元に一貫した主張をするのが当然であるとしたい気持ちは非常によくわかる。
だが、この基準を元に行われた格付けが適切な結果ではないとして、ある経済学者から批判が行われた(ある経済学者とは若田部昌澄氏のことで、批判は「経済学者たちの闘い」に記されている)。本書では、それに対し次のような反論が書かれている。
また、私のリポートを読んだある経済学者は、「痛快! である」としながらも、「けれども問題がある。最大の問題は、格付けの基準が『主張の一貫性』に求められていることだ」と指摘し、インフレ・ターゲット論者と不良債権処理論者が、同じく高い格付けを得たことを「珍妙な結果」と受け取った。
しかし、基準を仮に「主張の一貫性」に置いたのだから、異なる論を展開するエコノミストが同格とされたことを「珍妙な結果」と呼ぶことこそ「珍妙」なことだろう。
しかし、この反論が反論になっていないことは明らかである。仮にエコノミストの格付けを「身長」に置いた場合を考えてみるればよい。
しかし、基準を仮に「身長」に置いたのだから、同じ身長のエコノミストが同格とされたことを「珍妙な結果」と呼ぶことこそ「珍妙」なことだろう。
著者は一見、反論しているように見えるが、実際には話題をずらしているだけなのである。「ある経済学者」が珍妙な結果だといったのは「主張の一貫性」を元にしたエコノミストの格付け結果についてであって、そのメカニズムを問題にしているわけではない。ここで論点とすべきは「主張の一貫性」がエコノミストの格付けをするうえで適切かどうかという点にある。
では、「主張の一貫性」は、エコノミストを評価する上で適切な指標なのだろうか。答えは明確に「否」である。「主張の一貫性」では、エコノミスト(=経済の専門家)を適切に評価することはできないだけでなく誠実ささえも評価できない。このことを理解するために、サイエンティストを具体例として考えてみよう。
まず、評価の対象となるサイエンティストを選出することにする。ここは恣意的ではあるが、まともな物理学者代表としてアインシュタインを、トンデモさん代表として工学博士コンノケンイチを取り上げることにする。アインシュタインをトンデモ呼ばわりする人はさすがにいないだろうし、コンノケンイチがトンデモだと思わない人はこの文章を読むのをすぐに止め精神科にかかったほうがいいという意味で適切な人選であると私は考える。
まず、アインシュタインであるが彼は相対論や光電効果など物理学の中で極めて大きな位置を占める発見で知られる物理学の偉人である。だが、一般相対性理論をもとに作った「宇宙モデル」に当初組み込まれていた「宇宙項」をその後撤回し「宇宙項の導入はわが人生最大の不覚」という言葉を残したり、原子爆弾の開発をアメリカ大統領に求める手紙に署名しながら、後になってその行動を悔やんだなど「主張の一貫性」という観点で見た場合、最低の人物である。東谷氏の評価基準に従うなら落第点を免れないだろう。
それに対しコンノケンイチはどうだろうか。(著書をきちんとよんだことがないので)Web上の情報を読む限り、その処女作以降、ビックバンは存在せず、相対論は間違いであり、エーテルは存在するし、UFOの動作原理は反重力によるものだという見解は常に一貫しているように見受けられる。「主張の一貫性」を見ると極めて高い得点が得られるだろう。
このことからもわかるように、「主張の一貫性」による格付けは専門家としての格付けとして不適切である。しかも、アインシュタインの行動から分かるように、真に誠実な人間はたとえ正しくない主張をしたとしても、自分の過ちを直ちに認め意見を撤回するものである。他人に批判されようと自説を決して曲げないコンノケンイチと、間違いに気付き自説を撤回したアインシュタインのどちらが誠実なのだあろうか。このことは「エコノミストの誠実さを問題」とし、その基準として「主張の一貫性」を採用した東谷氏の論法に疑問をなげかけることになる*1。
*1) そもそも、東谷氏が「主張の一貫性」に基づいて採点しているのかという点自体疑わしいという話はある。良い悪いは別問題としても森永卓郎は一貫してハゲタカ・ファンド批判をしているし、竹中平蔵も「使える政策はなんでも使う」という点では極めて一貫性が高い。
経済学に国境はない
本書を読んでいると、一点非常に気になることがある。それは「アメリカ」についての部分だ。いくつか引用してみよう。
アメリカが最大の基準であるのは、政策レベルだけではない。科学的客観性をもつように見える「アカデミズム」の経済学においても、その傾向が強い。(p.22)
この経済学者氏は、自らが帰依するクルーグマンやバーナンキといった、アメリカのインフレ・ターゲット論の信者でない人々を、単に嫌悪しているにすぎない。自分が属する「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」とは異なるやりかたで、自分の発言が評されることを拒否したいだけなのだ。(p.27)
どうも東谷氏は「アメリカ経済学」や「日本経済学」みたいなものがあると考えているらしい。ジャーナリストならではの視点で非常に面白いが、残念ながらそんなものはない。それは、スティグリッツ経済学やマンキュー経済学といった欧米で一般的に使われているテキストが日本でも教科書として普通に採用されていることからも分かる通りである。私が知る限り、一般に科学と呼ばれる分野では国境という概念は極めて希薄である。「この経済学者氏」の言説が、まるで「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」に見えたとしても、それは単に現在の経済学研究の中心がアメリカ合衆国で行われているだけの話だ(しかも、アメリカが研究の中心地というだけで研究者の半分はアメリカ人でなかったりする)。経済学の主要な研究者がアメリカにおり、アメリカで最先端の研究が行われている現状で、経済学者が「経済学の主流派」としてアメリカ中心に議論されている論を主張したことが何か不思議なことなのだろうか。しかも、アメリカが研究の中心地になっているのは経済学に限らない、物理や工学でも多くの分野がアメリカを中心地として議論が行われている(もちろん、日本が中心地になっている分野もある)。もしこれを問題としたいならば、なぜ優秀な研究者が日本ではなくアメリカに集まるのかと言う点であって、「アメリカ経済学」に毒されているか否かではあるまい。
クルーグマンのインフレ目標策の論文などを読んでいれば分かることではあるが、経済学において理論のレベルではアメリカだからどうしたとか黄色人種だからこうしたなどという部分は出てこない。これは当たり前の話で、経済学も科学の端くれである以上、最低限の前提に従って現象を説明することが求められるからである(各国の消費性向の違いや貯蓄率の大きさなどはパラメータの値に反映される)。そもそも「アメリカだから」という概念が理論の中に含まれていないのに、どうして「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」などという批判が可能になるのだろうか。このような批判は、著者の東谷氏のナショナリズムに基づく空想の中だけで成立するのである。
経済学は経済を予測できるか
経済学が不信感を持たれている理由のひとつに「予測が当たらない」ということがあるように思う。本書でも、「バブル」「IT革命」といった経済事象に対し、エコノミスト達がどのように予測したのかを調査し検証を行っている。
確かに、「IT」という言葉に踊り、根拠なきニューエコノミー論を吹聴してまわった者達や深刻なデフレ時にも関わらずハイパーインフレ*2になるとなどと主張した者達は非難されてしかるべきである。とはいえ、経済はそもそも予測可能なのであろうか。私の知る限り、経済学は予測という点に関しては甚だ心許ない。少なくとも(天気予報のような)一般的な意味での予測ができないことは疑いあるまい。そもそも、そんなに簡単に経済の予測ができるのならば、経済学者の面々は今ごろ株で大いに儲けているはずであるし、予測が常に正しいならばどのような経済政策も実体経済を左右できないということになる。計量経済学のように予測することを主要な目的とする分野もあるにはあるが、その理論的な精密さにも関わらずうまくいっていないことは当の計量経済学の教科書に書かれている通りである。
なぜ、経済学は将来を予測できないのだろうか。理由はいくつかある。まず、ひとつは経済学の扱う範囲には「外部」の領域が多く存在するからである。物理学の教科書を開くと「初速5メートルで45度の方向にボールを打ち出すとき、どのような軌跡を描くか」などといった問題によく見かけるが、このような物理空間での物体の動きはニュートン力学を用いることで簡単に予測可能である。しかし、よくよく考えてみるとこの問題では、ボールが誰かに打ち落とされる、ボールが風に流される、撃ち出されたボールが消える魔球、などという可能性は考慮されていない。すなわち、この問題には「外部」がないのである。
物理学も経済学も同じ科学の仲間ということで基本的にその方法論、思考法は同じである。ただ、ひとつ大きな違いがあるとするならば「経済学では実験ができない」ことである。物理学の研究には真空や無風といった理想環境での実験が欠かせない。それに対し、経済学では理想環境での実験は基本的にはできないので、多くの雑音が混じった「歴史的データ」のみを用いて理論の検証を行わざるを得ない*3。
予測を行う場合でもこれと同様な問題が起こる。物理学を用いた予測が上手くいくのは「外部の要因が無視できるほど小さい」ため理想環境とほぼ同様に扱える場合が多いからである。だが、経済学ではどんな予測を行う場合でも外的要因の影響を無視することができない。今日のデータに基づいて「明日、景気が良くなるだろう」と予測しても、翌日に日銀が金融引締めをすればまったく逆の結果がでることになる。総理大臣や日銀総裁といった個人の行動如何によって経済環境が変化するわけだから、確実な予測などできるわけがない。
*2) ちなみに、ハイパーインフレは標準的な定義では年率13000%以上のインフレのことを指す……のだがあまり知られていないようだ。
*3) 近年では、コンピュータ上にシミュレーションを構築して実験することもあるらしい。
経済予測が上手くいかないもうひとつの理由は、「今日、手に入るデータは過去のものだけ」ということもあるだろう。経済予測の元となるデータは、月ごとや四半期ごとに政府の各機関や民間の研究所などから公表される。しかし、各個人が何を買ったかというデータや企業間の取引をリアルタイムでモニタのは物理的に不可能なので、データはある過去の一期間の総計として得られる。前述のように経済は日々起こる様々な事象により影響を受けるにも関わらず、予測に使用できるデータは先月以前のものだけなのである。
これらのことを踏まえて考えたとき、バブルやIT革命などへの予測だけを頼りに批判を行うというのは、必ずしも適切とは言えないかもしれない。バブルとは言うものの起こっていたのは株や土地の値段が上昇する資産インフレであって、経済自体は順調に成長していたのも事実である。バブル的状況はいつかは弾けるとはいえ、日銀さえ適切な金融政策を行っていれば被害が最小限に抑えられていた可能性は十分にあるだろう。それだけでなく、そもそもバブル的予想がファンダメンタルズを変えることで、バブルがバブルでなくなってしまうことさえも起こりえる*4。
また、ITによる生産性の成長は、ニューエコノミーなどということはなかったにしろ、やはりその影響が大きかったこともその後の研究で明らかになっている。低俗なエコノミストにより祭り上げられた経済現象は確かに虚像であったかもしれないが、マスコミによって貶められたそれもやはり虚像なのである。
*4) 稲葉振一郎氏の言を借りれば「なぜだかわからないがつり上がった株価・地価のおかげで(中略)会社の資金繰りが楽になり、技術革新投資を行って生産性を上げる」といったことが起こりえるのである。(稲葉振一郎著「経済学という教養」より)
経済学は役に立たないのか
前述のように、いかに経済学が頑張ろうともとても予測などできそうにはない。では、予測さえもできない経済学などというものは役に立たないのだろうか。当然そんなことはない。経済学は非常に役に立つし、実際役に立っているのである。予測できない経済学は役に立たないという主張は「ハサミは字を書くのに使えないから役に立たない」と言うも同然である。利用法を勘違いしているに過ぎない。
たしかに未来に何が起こるかは予測できないし、今の状態を正しく認識するのも難しい。だが、過去のデータはそろっているのだから、もし経済に何らかの法則があるならば、その法則を見つけ出し(政府の政策のような)主体的な行動をする際の指針にすることが可能である。
本書においても東谷氏は、経済学者の予測がはずれたことをいくつも挙げているが、その予測の内容が「将来はこうなる」というものなのか「この政策を行ったらこうなる」というものなのかで、その意味は大きく違う。前者は無理でも後者は十分可能であるし、そこでこそ経済学者がマスコミに登場する意義がある。
その意味で、経済学は「フィードバックの学問」である言えるかもしれない。経済学の理論を使ったからといって「来年のGDPを100兆円にするためには、税金を30%増やし国債を5%減らす」といったことは難しいが「景気が過熱したら沈静化する方向に、景気が減退したら加熱する方向に」といったフィードバック的な手法を用いることでより良い経済状態を作り出すことはできる。お風呂に例えるならば「42度にする」といったことはできないが、「温水」を足したり「冷水」を足したりすることでちょうどいい温度にするといった感じであろうか。
市場機構による最適化を方法論とした市場主義経済や財政政策、金融政策といった経済の調整法が、恐慌を過去のものとし経済の変動幅をより小くすることに成功したことを考えれば、その力は極めて大きなものであると言わざるを得ない。経済学がもたらした変化は一日単位で日々を過ごしている我々には実感が湧きにくいかもしれないが、ここ半世紀の経済発展が経済学ぬきに語れないのも事実なのである。
経済の良し悪しとは何か
知人との議論や様々なエコノミストの主張を通して気付かされるのは、経済学に基づき主張をする人とそうでない人とでは「景気」に対する認識がまったく異なっているということである。私にはこのことが経済学者の主張が理解されずトンデモエコノミストの主張が氾濫する最大の原因なのではないかと思えてならない。東谷氏は次の文章により本書を結んでいる。
私たちが現在の長期停滞を本格的に抜け出す方途も、思いつきのような唯一の手段を見つけてひたすら邁進することではなく、いくつものバランスのよい結合を見出すことからもたらされるのではないだろうか。
この一見もっともらしく見えながら曖昧極まりない結論も、経済の良し悪しとは何であるのかを理解していないことから起こった誤解である。経済の良し悪しをきちんと枠組みとして捉えていれば、いんちきエコノミストから提案される処方箋の大部分が的外れであることが自然と見えてくる。
では、経済学者は「経済の良し悪し」をいったいどのように捉えているというのだろうか。
ときどき象牙の塔から出てくるマクロ経済学者の多くと同じく、ぼくも実際のビジネスサイクルはリアル・ビジネスサイクルじゃないと思っているし、一部の(いやほとんどの)不況は、全体としての総需要が落ち込むせいで起こるんだと考える。
山形浩生訳 ポール・クルーグマン著「クルーグマン教授の経済学入門」より
ここでクルーグマンが不況の原因として「総需要の落ち込み」を挙げている点に注意して欲しい。経済学に基づかない議論を行うエコノミスト達が、しばしば「日本がダメになったから」不況になったのだと主張しているのとは対照的である。とは言っても後者のような「生産性の向上」に類する概念を経済学者がないがしろにしているわけではない。クルーグマンは同書の別の箇所で「経済にとって大事なことというのは、(中略)3つしかない。生産性、所得配分、失業、これだけ」と生産性が極めて重要な概念であることをはっきりと述べている。経済学を学んだことがないものからすると、この二つの文章は矛盾に満ちたもののように映るかもしれないが、もちろんそうではない。
このことを理解するには、経済の良し悪しが「生産性」と「需給バランス」という二つの異なる要因から決まることを理解する必要がある。では、経済学者の思考を垣間見るために、経済の良し悪しを学者よろしく多少理屈っぽく考えてみることにしよう。
世の中を見渡したとき、ここ百年の間に我々はずいぶん豊かな生活が可能になったと感じることだろう。ほんの一世紀前には最低限の食い物すら満足に手にできず、飢饉が起こる度に大量の餓死者が出ていたなど想像もできない。
豊かさとは何であるかを考えたとき、哲学的に考えるならばいろいろあるだろうが、経済学では「自分の欲しいものをより多く手に入れることができる状態」であると考える。(現実的には人間は物欲の塊なので「より多くの物が手に入る状態」と同義であると考えても良い。また、愛や恋などといった所謂「お金で買えない価値」であっても「愛と一万円どちらを取るか、一億円ならどうか、一兆円なら……」と順次比較することで「お金で買える価値」と比較可能となる。それにそもそも愛や恋がコストと無縁などという戯言、現代人ならば誰も信じまい)
豊かさが定義ができたので、次は「より豊かになるにはどうしたらいいか」を考える。単純に考えたら「より多く生産すればいい」と思うかもしれないが、これだけでは不十分である。今まで一人一日一個作っていたものを二人で二個作ったところで、一人あたりでは以前と変わらない。そこで出てくるのが「生産性」という概念である*5。例えば、以前一人で一日一個作っていたものが生産性が上がり一人で二個作れるようになったならば、以前に比べ二倍の物を手にすることができる。
*5) 経済学では生産性というが、意味的には生産効率と同義。
国全体の豊かさは基本的にこの「生産性」のみで決まる。科学技術の発展、道路網など交通手段の拡大、より効率的な組織構造など知的資産の蓄積とそれを基盤とする物的資産の利用により生産性が高まり、我々は以前に比べより多くの物を手にすることができるようになったのである。これを理解することで、ひとつの重要な知見が導きだせる。前述の通り、生産性は知的資産によって規定される。そのため、短期的には物的資産の欠損や遊休によって生産性が落ち込むことがあっても、長期的には「決して減少することがない」のである。日本が長期停滞の状態に陥っているにも関わらず、ほぼ毎年GDPが増加していることを不思議に思っている人もいるかもしれないが、携帯電話の登場や情報機器の高性能・低価格化などからもわかるように生産性自体は年々着実に向上しているのである。
では、生産性が「決して減少することがない」にも関わらず、なぜ不況という現象が発生してしまうのだろうか。それは、長期的に見れば決して減少しないにしても、「短期的には物的資産の欠損や遊休によって生産性が落ち込む」ことがあるからである。
その最も大きな要因は、何らかの理由により需要と供給のバランスがくずれてしまうことにある*6。クルーグマンが言うように需要が落ち込み、供給を下回った状況を想像してみてほしい。企業は、その時代の生産性にて可能な量・質の製品を製造し販売する。しかし、いくら製品を作ろうとも需要がないのでは、その部分がボトルネックとなってしまい商品を売り尽くすことができない。売上の低下は収益の低下に繋がり、収益の低下は賃金の低下に繋がる。そして、賃金の低下がさらに需要を押し下げてしまうことになる。こうしてさらに深刻化した需要の低下は、同じ経路を辿り生産量を引き下げることになる。
逆に太平洋戦後直後やオイルショック時のように供給が制限された場合はどうだろうか。この場合には、供給不足によって起こった商品の値上がりが需要の低下を引き起こすことになる。すなわち、需要と供給のどちらかが低下すると、その部分がボトルネックとなってしまい、経済は潜在的な能力を下回った状態でしか稼動ができなくなってしまう。
我々の生活が昔の人びとに比べずいぶん豊かになっているにも関わらず、GDPがマイナスになるような経済の停滞すなわち不況という悲劇に見舞われるのは、この需給ギャップによる経済活動の停滞という極めて目に見えにくい問題が原因となっているのである。
*6) 景気が悪い理由は需要が低下していることだが、景気が悪くなった(=需要が低下した)理由は必ずしもひとつではない。戦争による国土の荒廃、石油価格の上昇、増税、金融政策の失敗などのように分かりやすいものもあれば、景気の過熱により一時的に消費を遥かに上回る生産が行われてしまうことが原因になることもある。
構造改革では景気が回復できない理由
前章の議論から経済の良し悪しは、「長期的には、決して減少することがない」ことが判明したが、需給バランスの議論からはどのような知見が得られるのだろうか。
それは「生産性がいくら上がっても、需給ギャップによるロスがなくなるわけではない」ということである。需給ギャップによる損失は、絶対水準の低下ではなく稼働率の低下(相対的な水準の低下)である。今まで月産100個の製品を生産する能力がある工場が、需要不足により80個しか作っていなかったとする。だがこの状況で月産200個の製品を作れるように生産性を改善したところで(値段が半分になって倍売れるようになったと考えても)160個しか売ることはできない。確かに、生産性の向上分は経済は良くなっているものの、稼働率の低下から起こる損失が減るわけではない。実際にはそれどころか、生産性の向上によって供給サイドだけが活発化し、以前よりも需給ギャップが拡大してしまうことにもなりかねない。
構造改革とは、前者の「生産性」を向上させる政策である。もし、現在が生産性の伸びが極めて低下したことが原因で経済が停滞しているならば、構造改革で景気回復という主張も納得がいく。だが、1998年、2001年には経済成長率マイナスすら記録しているし、立場的に日本とほぼ同レベルの経済水準にあるはずのアメリカはたしかに成長の伸びは鈍化しているとはいえ、日本より遥かにましな経済成長率を達成している。このことを考えると、経済低迷の原因を生産性の伸び率低下に求めるのは難しい。
また、経済学の観点から見れば、生産性の伸び率の低下が経済低迷の原因だとすると、現在の状況は古典経済学が考えていたような完全雇用状態であるということになる。だがこの状況では「就職したい人は適切な賃金さえ要求すればいつでも就職でき」、「インフレ・デフレは経済に影響を与えない」はずである。このことを考えれば、現在の状況が完全雇用状態であるなどということはとても考えられない。
とはいえ、構造改革として挙げられる「行政改革」や「金融改革」などといった施策は、国家を長期的に成長させるためには必要不可欠な要素である。日本の長期的な行き先を憂いている政治家の皆様なら、今の幸福を捨ててでも、未来を良くすべきであると思うのも理解できなくはない。
だが、ケインズが言うように「我々は長期的には皆死んでいる」のだ。少なくとも今食うのにすら困っている人がいるなら、それを解決するのが優先であろう。しかも、構造改革は景気回復と二律背反ではない*7。構造改革を行いながら、景気を回復させることには何ら問題がない。しかし、経済が悪化し続けているにも関わらず構造改革だけを断行するならば、クルーグマンの言うように「小泉政権の絶対的スローガンは“改革か破滅か”である。しかし、実際の結果が“改革したら破滅”になってしまう可能性は危険なほど高い」のである。
*7) 世の中ではなぜかリフレ派が構造改革に反対していると思っている人がいるようだが、それは大きな勘違いである。リフレ派はどっちもやれと言っているのである。
景気を回復させるには
このように言うと驚く人もいるかもいるかもしれないが、実のところ景気を回復させるための方法というのは、たった二つしか存在しない。「財政政策」と「金融政策」である*8。
前述のように、(不況の起因は別としても)不況が続く原因は「需要の低下」にある。で、あるならば対策は「需要の回復」を行うだけである。需要は、個別に見ると日々我々が行っている「消費」であったり、企業が未来の成長のために行う「投資」であったりする。もし政府がこれらの要素を操作できるのであれば、景気を回復させることが可能ということになる。
*8) これを知ってると、なんで経済論戦がこんなに混乱しているのか不思議でならなくなる。
まずは、「財政政策」。小渕政権時には極めてもてはやされたにも関わらず、最近不人気な財政政策であるが、これは国民に代わって政府が投資を行うという政策である(減税も政府のお金を民間に流して消費を増やすという意味で財政政策の一種と考えられる)。財政政策が国民の多くに人気がない理由は「無駄な公共事業が多い」という一点につきると思うが、実は経済を回復させるという意味で言えば用途がどうだろうと関係はない。例えば、政府が金を10兆円土建屋さんに注ぎ込むと、土建屋さんの収益は改善する。だが、これで終りではない。収益の改善により今度は土建屋が新しい投資を行うかもしれないし、給料が増加して従業員が消費を増やすかもしれない。こうして起こった需要の増加が他の産業の収益を改善させ結果的に「当初注ぎ込んだお金以上に需要を増やす」ことになる。
これが本書にも出てくる「乗数効果」であり、経済学者の試算によれば最初に注ぎ込んだ金額の10倍程度の効果が出るため、赤字国債を発行しても十分元が取れるとされる。小渕政権時の大規模な財政政策により、一時的とはいえ景気が改善したことを思い出せば、財政政策に効果があることに自体には疑問の余地はない。
だが、この財政政策という20世紀前半から存在する古き良き経済政策は、現在においては当の経済学者自身からも人気がないのである。理由は、本書にも書かれている通りで、「たとえ財政政策を行っても将来増税が待っているならば、今の消費を増やさない方が合理的選択となる」という逆ケインズ効果や、現在の日本のように深刻なデフレ期待がある場合には注ぎ込んだお金がほぼ貯蓄に回るという打ち消し効果が現れるなどの理由により(少なくと今の日本では)極めて低い乗数効果しか現れないことが明らかになってきたからである。内閣府の政策研究官 原田泰氏の試算によれば、ここ十年間に行われた日本の財政政策の乗数は0.5~1.5程度であり、とても10倍などという効果は出ないとのことである。
有効性に疑問の出てきた財政政策に代わり現れてきたマクロ経済学者おすすめの秘密アイテム、それが「金融政策」である。
金融政策は「国家はお金の価値を操作できる」という特権を駆使することで金利を変え投資量を変化させる政策である*9。我々はお金の価値が変わらないと考えがちであるが、大学で経済学の授業を受けるとまず教えられるのは「お金の価値は変化する」ということである。
ハイパーインフレが起こったことでお金が恐ろしい勢いで紙切れ同然になっていく映像を見たことのある人もいるかもしれない。日本のようなまっとうな国家ではそのようなことはなかなか起きないが、お金を銀行に預ければ金利がつくし、インフレやデフレが購買力に関わってくることくらいは理解できるだろう。インフレやデフレは、物価価格の変化という側面から説明されることが多いが、物価が上がれば買える物が少なくなる、すなわち「お金の価値が下がる」わけだから、それはお金の価値の変化と言い換えることができる。
通常、金融政策は政府の一機関である中央銀行により行われる(日本では日本銀行がそれにあたる)。中央銀行は、お札の印刷と金融機関へのお金の貸し出しを行う機関である。そのため、作ろうと思えばいくらでも「本物の」お金を作ることができる。お金の価値を操作する方法はいくつかあり、有名なのは「公定歩合の変更」であろう。これは、お金の入り口である各銀行への貸し出し金利を変更することでベースとなる価値を上げ下げする政策である。もうひとつは、量的緩和というもので、これは市場原理に基づきお金の供給量を増やすことで価値を下げる(=金利を下げる)という手法である。
中央銀行は、景気が悪い時には金利を下げ、景気過熱時には金利を上げることで投資を制御し経済の安定的な運営を行うのである。金融政策は、野口旭の言うように現在世界的に最も主流な経済安定化手法となっている。
*9) 実は為替もこの金融政策により決まるため、為替政策と呼ばれるものは金融政策の裏側のような存在でしかない。為替レートは、二国間のマネタリーベース(お金の量)の比で決まる。財務省が度々介入するにも関わらず数日で元のレートに戻ってしまうのは、これが理由である。
ただ、この金融政策も磐石というわけではない。金利の変化が、経済に実に大きな影響を与えることは過去のデータからわかっているが、我々庶民には直感的でないこともありなかなか理解されない。庶民に理解されないだけならいいが、残念ながら政治家、そして当の日本銀行の人びとにも理解されにくいようである。
問題は、それだけではない。本書でも小宮隆太郎氏の言を引用し金融政策に対する疑惑を提示しているが、「深刻な不況期には効果が弱まる」という問題は経済学者の一致した見解であるし、開放経済下ではその有効性が低下するのも確かである。また、クルーグマンの言う「流動性の罠」による金融政策無効論は、日本の置かれている深刻なデフレ不況時には金融政策の効果が限定的であることを示している。
それでも、インフレ・ターゲットで景気は回復する
財政政策もダメ、金融政策もダメ……では、どうすればいいのか。ひとつは諦めることである。だが、多くの人はこの結論に納得すまい。他に打つ手はないのか。
もちろん、ある。もう一度よく読んで欲しいのだが、財政政策も金融政策も「まったく効かない」とは書いていない。確かに効果は通常時ほど大きくはないが効かないわけではないのだ。もし景気回復を諦めないのであれば、我々はその手段として「財政政策」と「金融政策」に頼るしかない。スティグリッツ経済学にも次のように書いてある。
(金融政策が深刻な不況期には効果が弱まるということに関して)しかしながら、金融政策の擁護者たちは、重要なのは金融政策に何らかの効果があるということである、と主張している。彼らにとっては、(マネーサプライの増加がもたらす)効果が弱いということは、金融当局はより積極的な行動をとるべきである、ということを意味しているにすぎない。*10
ジョセフ・E・スティグリッツ著 藪下史郎など訳「マクロ経済学第2版」より
*10) 研究・調査が進んだ結果、現在ではこの「金融政策の擁護者」の立場が大勢となっている。この共通認識の確立に日本の長期停滞がおおいに影響を与えたことは言うまでもない。
ただ、ここで次の二点を考慮する必要がある。
景気が回復するまで政策を持続できるか
弱まった政策効果を回復させる手段はないか
前者の「景気が回復するまで政策を持続できるか」という点であるが、ただでさえ効果が限定的なのだから、需給バランスがきちんととれるまでずっと政策を継続できることが求められるということである。だが、ここで財政政策は問題となる。現在の日本の状況を見ればわかるように、大規模な財政政策を行うには国債を発行することで費用を賄う必要がある。だが、その金額は日本銀行やIMFなどの試算で25兆円、米FRBのバーナンキの試算では130兆円ほどにもなるとも言われている。ただでさえ厳しい財政状況の中、多額の資金を捻出し、それでもなお景気が回復しないようであればさらに国債を発行し続けなければならないというのは政治的にも経済的にもあまり考えたくない状況であろう。それに対して金融政策には、このような制限はない。お金の価値を下げたければ、好きなだけお札を刷ればよいし、インフレ率が高くなりすぎたら銀行への貸し出し金利を引き上げることで、いくらでもインフレ率を下げることができる。
それでは、後者の「弱まった政策効果を回復させる手段はないか」という点を考えてみよう。たしかに金融政策をすごい規模で行い続ければいつかはインフレになり投資が促進され景気は回復するだろう。だが、もし弱まった政策効果を高めることができるのであればそれに越したことはない。そこで出てくるのがインフレ目標策*11である。
現在、日本で金融政策が効きにくい最大の理由は、金利の0%制約による流動性の罠的状況と強力なデフレ期待(今後、デフレが続くだろうという予想)が存在することにある。例えば、来年5%のデフレになると思うならば、5%に満たない利益しか得られないような投資を行うよりも現金を持つ方がお得ということになる(リスクを考えるならば、もっと大きい利益でも投資を控えるだろう)。このようにインフレ(デフレ)率を考慮した金利を「実質金利」と言うが、日銀の貸し出し金利がすでに0%になってしまっている今の状況ではこれ以上の引き下げができないため、デフレ期待の分だけ実質金利は高くなる。
インフレ目標策とは人びとに将来インフレになると予測させることでこの実質金利を引き下げ消費や投資を促進する政策である。もし明日ハイパーインフレになるならば、皆今日中にお金を使い切るだろう。これは極端だが、方法論としては同じことである。しかも、本当にインフレ率が高くなってしまうようであれば、逆に金融引き締めを行ってインフレ率はいくらでも下げることができる。東谷氏は「インフレ目標に前例がない」ことを非常に気にしておられるようだが、こと引き締めに関してはその実績に事欠かない。
インフレ目標策を用いれば、このようなフィードバック的手法によりインフレ率を数%というマイルドな水準に留めることが可能になる(岩田喜久男などが挙げる3%程度のインフレ率と言うのは、過去のデータから見て最も安定的な経済成長が可能になるインフレ率でもある)。
*11) インフレ目標策に関してはリフレFAQ「余は如何にして利富禮主義者となりし乎」を参考のこと
このように論理的に有効性が明らかに思えてもなお、インフレ目標策は東谷氏の言うように「理論的にも実証的にも保証のない政策」なのだろうか。
少なくとも理論的に保証があるのは確実だ。なんせ論文だけ書いて暮らしているマクロ経済学者達のお墨付きをもらっているのだ。また、東谷氏の引用する小宮隆太郎氏の「深刻な不況期には効果が弱まる」という批判は、そもそもインフレ目標策が「そのような状況でも金融政策を有効にする」ために提案されたことを考えれば的外れと言わざるを得ない。
では実証面ではどうだろうか。たしかにこの面ではインフレ目標策が頼りないのも確かである。ニュージーランドでの成功例や、恐慌時の研究を通して裏付けは学会的には十分あるかもしれないが、ジャーナリストでも納得できるような分かりやすい話ではない。ただ、ここ半世紀は知っての通りインフレの時代であって、デフレになった国自体がほとんどない以上、仕方のないところもある。
しかし、「インフレ目標」のリスクを判断することで、実施する価値があるかどうかは十分に判断できる。前述の通り、インフレ目標によって高率のインフレになることは有り得ない。それならば、インフレ目標が失敗と判断される状況では何が起こるのだろうか。それは「何も起こらない」ということである。だが、これすらもバーナンキの背理法*12を使えば即座に否定できる。
すなわち、インフレ目標策を適切に運用すれば日本は「必ず」不況から抜け出すことができるのである。
*12) 「中央銀行が国債を含む資産を買いつづけてもインフレにならない(=お金の価値が下落しない)」と仮定する。すると、中央銀行は世界中の資産を買い占めることが可能になり、政府は無税で国家を運営できるようになる。こんなことはありえないので、最初の命題は否定される。すなわち、「中央銀行が国債を含む資産を買いつづければ、必ずインフレになる」のである。
エコノミストの評価は経済学で
東谷氏の最大の問題は、科学の力、ひいては学問の力を理解していないことにある。たしかに、ひとりひとりを見れば現実を知らない議論をする学者も少なくない。しかし、総体としての学問は、数百年という期間に渡ってデータを調べ、理論化し、検証するという作業の積み重ねを経て集積されたものである。まさに人類が歴史から手に入れた知的資産そのものなのである。
学問が人類の知的資産であるということは、学問を用いても理解できない物事は誰も確かなことを知らないということを意味する。もし誰かが学問で説明できないことを説明できたとしても、それは単なる思いつきか勘違いである可能性が高い。まれに真実だったりすることもあるが、それは理論化もなされていなければ、検証もすんでいない段階の思考である。他人を十分説得できるほどの信頼性をまだ獲得できていないはずのものである(信じるのは勝手だが)。
東谷氏は、エコノミストの格付けをもくろんだわけだが、エコノミストは評論家である前に経済の専門家であるはずである。当然、その評価は如何に適切な経済の知識、見識を持っているかに寄らねばならない。
では、適切な経済の知識・見識とは何であろうか。当然、それは人類の知的資産たる経済学である。物理学に基づかない議論をするサイエンティストをあなたは信用するだろうか。経済学に基づかない議論を行うエコノミストがいる現状の非常識に気付いてこそ、はじめて信頼に値する格付けが可能になるのである。
おわりに
長々と批判を行ってしまったが、前述の通りこの「エコノミストは信用できるか」という本は良書である。その時々でなされるエコノミストの言説を保存・整理するという作業は、本職の経済学者ではできないジャーナリストならではの仕事であり、賞賛されてしかるべきであるように思う。私がこの文章を書こうと思ったのも、本書がトンデモ本ではなかったからである。トンデモ本であればたとえ内容を信じてしまっても、読解力のない読者の責任であろう。しかし、本書のように証拠資料を元にし、学会では通用しなくともジャーナリストとしては適切な文章で書かれては、真相を求め知識を探求する人の妨げになるかもしれない。
すでに日本は失われた十年どころではない長期停滞のただ中にいる。これ以上、インフレ目標策の採用が先延ばしにされ不適切な経済運営が行われるなどということがあってはならない。日本銀行がその実行を躊躇しつづける以上、我々国民ひとりひとりが経済学の正しい知識を身に付け政府に圧力をかけつづけることが重要である。(消極的だと思うかもしれないが、これくらいしか方法が思いつかないのである)
政府が経済学に基いた合理的な経済運営を行うことこそ、真の構造改革である。一日も早くそのような日が来ることを私は願ってやまない。
2004/01/10 英-Ran
--------------------------------------------------------------------------------
質問とその回答
Q. この本を良書だと言っていますが、最後にはこの本が誤解を生みかねない危険性にふれています。こういう危険な本を「良書」と呼べるのでしょうか。
A. 何をもって「良書」と呼ぶかは人によっていろいろあるかと思いますが、私は著者の東谷氏があくまでジャーナリストであるという点を考慮しています。ジャーナリストの仕事は、真実を追うことと思われがちですがジャーナリストの名著と呼ばれるものを何冊か読む限りでは、重要なのは「人びとが思っていることをデータで裏付け、説得力のある形で提示すること」にあるのではないかと感じています(すなわち、真実は説得力を得るために必要ではあるけど必須というわけではない)。真実を追い求めるのは学者や警察の仕事であるわけですから、そもそも真実を追い求めることを目的とするならジャーナリストはほとんど失業してしまいます。
著者の東谷氏が本書で追い求めた点は「エコノミストの奴らってのはみんな不誠実なんだぜ」という多くの人が薄々感じていたことを説得力ある形で提示することだったのではないかと思います(だからこそ、どのエコノミストの主張にも反対の立場をとる)。そう考えると、本書に掲載されているエコノミストたちの発言は、十分に説得力を持つ形で提示されているように思います。
また、たしかに著者の主観が反映されている部分も多いとはいえ、その論法の多くは「Aの主張に対してBはこのように反論しているから、Aには疑念がある」というものであり、東谷氏自身が必ずしも間違った主張をしているわけではないことにも注意が必要です。
それ以上に、エコノミストの発言を追うことで問題あるエコノミストを炙り出すという手法は、(今までなかったのが不思議ではあるけれど)東谷氏が最初に行ったのであり、その開拓者としての評価は十分可能であるかと思います。
マルクスの資本論が危険なように、この本は良書だからこそ危険なのです。人の心を引きつけない本は、そもそも読まれないので、たとえ間違っていてもその主張が広まる心配はない。リフレ派は100年デフレやら国債暴落やらも相手にしていますが、ああいった類の本は「ノストラダムスの大予言」がそうであったように、実のところみんなそんなに信じてるわけありません(本当に信じているのなら、今頃民族大移動が起こっているだろう)。本当に危険なのは、この本のように一抹の真実(と根本的な誤解)が含まれている本なのだと私は考えます。
更新履歴
[2004/01/12]
タイトルが「エコノミストの誤謬」となっていましたが、書き間違いでした。正しくは上記の通り「ジャーナリストの誤謬」です。
「エコノミストは『主張の一貫性』で評価されるべきか」の章にて「ある経済学者とは、野口旭のことであると思われる」と書きましたが、実際には「経済学者たちの闘い」からの引用であることが判明しましたので修正を行いました。
[2004/01/13]
「景気を回復させるには」の章で、財政政策を19世紀前半と書いていましたが、正しくは20世紀前半です……ここは割と念入りに調べたはずなんだけどなぁ。最初1900年代前半と書いてあったのを校正中に間違えて修正してしまったらしい。
[2004/01/15]
「はじめに」にて「著者の東谷氏は十年にもわたりエコノミストの言説を追う中で、論点となっているのが『構造改革 VS インフレ目標』であることをきちんと見抜いている」と書きましたが、たしかに金融政策とインフレ目標にページを大きく割いてはいるものの対立軸を見抜いているというのはいいすぎのようにも感じられるので「『インフレ目標』が大きな争点のひとつになっていることをきちんと見抜いている」という文章に修正しました。
目次
はじめに
エコノミストは「主張の一貫性」で評価されるべきか
経済学に国境はない
経済学は経済を予測できるか
経済学は役に立たないのか
経済の良し悪しとは何か
構造改革では景気が回復できない理由
景気を回復させるには
それでも、インフレ・ターゲットで景気は回復する
エコノミストの評価は経済学で
おわりに
--------------------------------------------------------------------------------
質問とその回答
更新履歴
Top
Copyright c 2004 英-Ran
- 東谷暁「エコノミストは信用できるか」を検討する -
〔出典:http://www.asahi-net.or.jp/~dp8h-izn/economist.html〕
本文章の文責は英-Ranにあります。ご意見、ご感想、ご批判などはarn@cafe.email.ne.jpまでお願いします。本文章は著作権や出所が明示される限りにおいて、自由に配布して頂いてかまいません。
はじめに
東谷暁というジャーナリストが書いた「エコノミストは信用できるか」という本がある。この本は、誤解に基づくインフレ目標批判をしていることもあって、真っ当な経済学徒の評判は極めてよろしくない。しかし私の読んだ限りでは、この本は紛れもなく良書である。各種経済論理をまとめあげ整理したその手腕、努力は間違いなく賞賛に値する。
本書の特徴はエコノミストの主張の一貫性を頼りに「エコノミストの格付け」を行う点にある。数多くのエコノミストの言論を記録し、その変遷を調査することによって不誠実なエコノミストをあぶり出すという行為は確かに重要である。日本最大の経済紙、日経新聞のいい加減さを白日の下に晒した点などを考えれば、著者の東谷氏は画期的な仕事をしたのではないかとさえ思える。言論の自由は「目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない」という効果が現れるからこそ意味がある。学問の歴史が論争の歴史であることからもわかるように、本書のようなフィードバックがあってはじめて正しい言論が保たれるのだ。
また、本書では多くの部分を「金融政策」あるいは「インフレ目標論」に割いている。リフレ派にとっては当たり前のことのように思えるが、これは画期的なことである。現在の「世間知」を作り出している新聞、あるいはテレビといったマスコミを言論の中心として見た場合、その論点は「構造改革 VS 財政政策」であって決して「構造改革 VS インフレ目標」ではない。インフレ目標論は読売新聞が全面的に押し出しているはいるものの、未だに中心的論説にはなりえていない。
しかし、著者の東谷氏は十年にもわたりエコノミストの言説を追う中で、「インフレ目標」が大きな争点のひとつになっていることをきちんと見抜いている。それだけではなく、良いデフレ論への批判や「『構造改革』という言葉で指摘されるものが、いったい何を意味していたのか」など鋭い指摘も多い。たとえ、経済学の知識がなくともきちんと調べさえすれば適切な議論に近づくことができるのである。
だが、これほど入念な調査を行ったにも関わらず、本書の出した結論や指摘を「正しさ」という基準で見た場合、多くの誤りを含むのも事実である。なぜ正しくないのか。なぜ正しい結論に辿りつけないのか。ここでは、本書の内容に批判・検討・補足を加えながら、その問題点を明らかにしたい。
エコノミストは「主張の一貫性」で評価されるべきか
本書において、著者は「主張の一貫性」という基準に基づきエコノミストに対して評価するとしている。確かに一見、この主張は正しそうに見える。通常、時と場合によって言論をころころと変える人は不誠実と見なされる。エコノミストが経済の専門家であるなら唯一確実な真実を元に一貫した主張をするのが当然であるとしたい気持ちは非常によくわかる。
だが、この基準を元に行われた格付けが適切な結果ではないとして、ある経済学者から批判が行われた(ある経済学者とは若田部昌澄氏のことで、批判は「経済学者たちの闘い」に記されている)。本書では、それに対し次のような反論が書かれている。
また、私のリポートを読んだある経済学者は、「痛快! である」としながらも、「けれども問題がある。最大の問題は、格付けの基準が『主張の一貫性』に求められていることだ」と指摘し、インフレ・ターゲット論者と不良債権処理論者が、同じく高い格付けを得たことを「珍妙な結果」と受け取った。
しかし、基準を仮に「主張の一貫性」に置いたのだから、異なる論を展開するエコノミストが同格とされたことを「珍妙な結果」と呼ぶことこそ「珍妙」なことだろう。
しかし、この反論が反論になっていないことは明らかである。仮にエコノミストの格付けを「身長」に置いた場合を考えてみるればよい。
しかし、基準を仮に「身長」に置いたのだから、同じ身長のエコノミストが同格とされたことを「珍妙な結果」と呼ぶことこそ「珍妙」なことだろう。
著者は一見、反論しているように見えるが、実際には話題をずらしているだけなのである。「ある経済学者」が珍妙な結果だといったのは「主張の一貫性」を元にしたエコノミストの格付け結果についてであって、そのメカニズムを問題にしているわけではない。ここで論点とすべきは「主張の一貫性」がエコノミストの格付けをするうえで適切かどうかという点にある。
では、「主張の一貫性」は、エコノミストを評価する上で適切な指標なのだろうか。答えは明確に「否」である。「主張の一貫性」では、エコノミスト(=経済の専門家)を適切に評価することはできないだけでなく誠実ささえも評価できない。このことを理解するために、サイエンティストを具体例として考えてみよう。
まず、評価の対象となるサイエンティストを選出することにする。ここは恣意的ではあるが、まともな物理学者代表としてアインシュタインを、トンデモさん代表として工学博士コンノケンイチを取り上げることにする。アインシュタインをトンデモ呼ばわりする人はさすがにいないだろうし、コンノケンイチがトンデモだと思わない人はこの文章を読むのをすぐに止め精神科にかかったほうがいいという意味で適切な人選であると私は考える。
まず、アインシュタインであるが彼は相対論や光電効果など物理学の中で極めて大きな位置を占める発見で知られる物理学の偉人である。だが、一般相対性理論をもとに作った「宇宙モデル」に当初組み込まれていた「宇宙項」をその後撤回し「宇宙項の導入はわが人生最大の不覚」という言葉を残したり、原子爆弾の開発をアメリカ大統領に求める手紙に署名しながら、後になってその行動を悔やんだなど「主張の一貫性」という観点で見た場合、最低の人物である。東谷氏の評価基準に従うなら落第点を免れないだろう。
それに対しコンノケンイチはどうだろうか。(著書をきちんとよんだことがないので)Web上の情報を読む限り、その処女作以降、ビックバンは存在せず、相対論は間違いであり、エーテルは存在するし、UFOの動作原理は反重力によるものだという見解は常に一貫しているように見受けられる。「主張の一貫性」を見ると極めて高い得点が得られるだろう。
このことからもわかるように、「主張の一貫性」による格付けは専門家としての格付けとして不適切である。しかも、アインシュタインの行動から分かるように、真に誠実な人間はたとえ正しくない主張をしたとしても、自分の過ちを直ちに認め意見を撤回するものである。他人に批判されようと自説を決して曲げないコンノケンイチと、間違いに気付き自説を撤回したアインシュタインのどちらが誠実なのだあろうか。このことは「エコノミストの誠実さを問題」とし、その基準として「主張の一貫性」を採用した東谷氏の論法に疑問をなげかけることになる*1。
*1) そもそも、東谷氏が「主張の一貫性」に基づいて採点しているのかという点自体疑わしいという話はある。良い悪いは別問題としても森永卓郎は一貫してハゲタカ・ファンド批判をしているし、竹中平蔵も「使える政策はなんでも使う」という点では極めて一貫性が高い。
経済学に国境はない
本書を読んでいると、一点非常に気になることがある。それは「アメリカ」についての部分だ。いくつか引用してみよう。
アメリカが最大の基準であるのは、政策レベルだけではない。科学的客観性をもつように見える「アカデミズム」の経済学においても、その傾向が強い。(p.22)
この経済学者氏は、自らが帰依するクルーグマンやバーナンキといった、アメリカのインフレ・ターゲット論の信者でない人々を、単に嫌悪しているにすぎない。自分が属する「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」とは異なるやりかたで、自分の発言が評されることを拒否したいだけなのだ。(p.27)
どうも東谷氏は「アメリカ経済学」や「日本経済学」みたいなものがあると考えているらしい。ジャーナリストならではの視点で非常に面白いが、残念ながらそんなものはない。それは、スティグリッツ経済学やマンキュー経済学といった欧米で一般的に使われているテキストが日本でも教科書として普通に採用されていることからも分かる通りである。私が知る限り、一般に科学と呼ばれる分野では国境という概念は極めて希薄である。「この経済学者氏」の言説が、まるで「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」に見えたとしても、それは単に現在の経済学研究の中心がアメリカ合衆国で行われているだけの話だ(しかも、アメリカが研究の中心地というだけで研究者の半分はアメリカ人でなかったりする)。経済学の主要な研究者がアメリカにおり、アメリカで最先端の研究が行われている現状で、経済学者が「経済学の主流派」としてアメリカ中心に議論されている論を主張したことが何か不思議なことなのだろうか。しかも、アメリカが研究の中心地になっているのは経済学に限らない、物理や工学でも多くの分野がアメリカを中心地として議論が行われている(もちろん、日本が中心地になっている分野もある)。もしこれを問題としたいならば、なぜ優秀な研究者が日本ではなくアメリカに集まるのかと言う点であって、「アメリカ経済学」に毒されているか否かではあるまい。
クルーグマンのインフレ目標策の論文などを読んでいれば分かることではあるが、経済学において理論のレベルではアメリカだからどうしたとか黄色人種だからこうしたなどという部分は出てこない。これは当たり前の話で、経済学も科学の端くれである以上、最低限の前提に従って現象を説明することが求められるからである(各国の消費性向の違いや貯蓄率の大きさなどはパラメータの値に反映される)。そもそも「アメリカだから」という概念が理論の中に含まれていないのに、どうして「アメリカ経済学コミュニティ日本支部」などという批判が可能になるのだろうか。このような批判は、著者の東谷氏のナショナリズムに基づく空想の中だけで成立するのである。
経済学は経済を予測できるか
経済学が不信感を持たれている理由のひとつに「予測が当たらない」ということがあるように思う。本書でも、「バブル」「IT革命」といった経済事象に対し、エコノミスト達がどのように予測したのかを調査し検証を行っている。
確かに、「IT」という言葉に踊り、根拠なきニューエコノミー論を吹聴してまわった者達や深刻なデフレ時にも関わらずハイパーインフレ*2になるとなどと主張した者達は非難されてしかるべきである。とはいえ、経済はそもそも予測可能なのであろうか。私の知る限り、経済学は予測という点に関しては甚だ心許ない。少なくとも(天気予報のような)一般的な意味での予測ができないことは疑いあるまい。そもそも、そんなに簡単に経済の予測ができるのならば、経済学者の面々は今ごろ株で大いに儲けているはずであるし、予測が常に正しいならばどのような経済政策も実体経済を左右できないということになる。計量経済学のように予測することを主要な目的とする分野もあるにはあるが、その理論的な精密さにも関わらずうまくいっていないことは当の計量経済学の教科書に書かれている通りである。
なぜ、経済学は将来を予測できないのだろうか。理由はいくつかある。まず、ひとつは経済学の扱う範囲には「外部」の領域が多く存在するからである。物理学の教科書を開くと「初速5メートルで45度の方向にボールを打ち出すとき、どのような軌跡を描くか」などといった問題によく見かけるが、このような物理空間での物体の動きはニュートン力学を用いることで簡単に予測可能である。しかし、よくよく考えてみるとこの問題では、ボールが誰かに打ち落とされる、ボールが風に流される、撃ち出されたボールが消える魔球、などという可能性は考慮されていない。すなわち、この問題には「外部」がないのである。
物理学も経済学も同じ科学の仲間ということで基本的にその方法論、思考法は同じである。ただ、ひとつ大きな違いがあるとするならば「経済学では実験ができない」ことである。物理学の研究には真空や無風といった理想環境での実験が欠かせない。それに対し、経済学では理想環境での実験は基本的にはできないので、多くの雑音が混じった「歴史的データ」のみを用いて理論の検証を行わざるを得ない*3。
予測を行う場合でもこれと同様な問題が起こる。物理学を用いた予測が上手くいくのは「外部の要因が無視できるほど小さい」ため理想環境とほぼ同様に扱える場合が多いからである。だが、経済学ではどんな予測を行う場合でも外的要因の影響を無視することができない。今日のデータに基づいて「明日、景気が良くなるだろう」と予測しても、翌日に日銀が金融引締めをすればまったく逆の結果がでることになる。総理大臣や日銀総裁といった個人の行動如何によって経済環境が変化するわけだから、確実な予測などできるわけがない。
*2) ちなみに、ハイパーインフレは標準的な定義では年率13000%以上のインフレのことを指す……のだがあまり知られていないようだ。
*3) 近年では、コンピュータ上にシミュレーションを構築して実験することもあるらしい。
経済予測が上手くいかないもうひとつの理由は、「今日、手に入るデータは過去のものだけ」ということもあるだろう。経済予測の元となるデータは、月ごとや四半期ごとに政府の各機関や民間の研究所などから公表される。しかし、各個人が何を買ったかというデータや企業間の取引をリアルタイムでモニタのは物理的に不可能なので、データはある過去の一期間の総計として得られる。前述のように経済は日々起こる様々な事象により影響を受けるにも関わらず、予測に使用できるデータは先月以前のものだけなのである。
これらのことを踏まえて考えたとき、バブルやIT革命などへの予測だけを頼りに批判を行うというのは、必ずしも適切とは言えないかもしれない。バブルとは言うものの起こっていたのは株や土地の値段が上昇する資産インフレであって、経済自体は順調に成長していたのも事実である。バブル的状況はいつかは弾けるとはいえ、日銀さえ適切な金融政策を行っていれば被害が最小限に抑えられていた可能性は十分にあるだろう。それだけでなく、そもそもバブル的予想がファンダメンタルズを変えることで、バブルがバブルでなくなってしまうことさえも起こりえる*4。
また、ITによる生産性の成長は、ニューエコノミーなどということはなかったにしろ、やはりその影響が大きかったこともその後の研究で明らかになっている。低俗なエコノミストにより祭り上げられた経済現象は確かに虚像であったかもしれないが、マスコミによって貶められたそれもやはり虚像なのである。
*4) 稲葉振一郎氏の言を借りれば「なぜだかわからないがつり上がった株価・地価のおかげで(中略)会社の資金繰りが楽になり、技術革新投資を行って生産性を上げる」といったことが起こりえるのである。(稲葉振一郎著「経済学という教養」より)
経済学は役に立たないのか
前述のように、いかに経済学が頑張ろうともとても予測などできそうにはない。では、予測さえもできない経済学などというものは役に立たないのだろうか。当然そんなことはない。経済学は非常に役に立つし、実際役に立っているのである。予測できない経済学は役に立たないという主張は「ハサミは字を書くのに使えないから役に立たない」と言うも同然である。利用法を勘違いしているに過ぎない。
たしかに未来に何が起こるかは予測できないし、今の状態を正しく認識するのも難しい。だが、過去のデータはそろっているのだから、もし経済に何らかの法則があるならば、その法則を見つけ出し(政府の政策のような)主体的な行動をする際の指針にすることが可能である。
本書においても東谷氏は、経済学者の予測がはずれたことをいくつも挙げているが、その予測の内容が「将来はこうなる」というものなのか「この政策を行ったらこうなる」というものなのかで、その意味は大きく違う。前者は無理でも後者は十分可能であるし、そこでこそ経済学者がマスコミに登場する意義がある。
その意味で、経済学は「フィードバックの学問」である言えるかもしれない。経済学の理論を使ったからといって「来年のGDPを100兆円にするためには、税金を30%増やし国債を5%減らす」といったことは難しいが「景気が過熱したら沈静化する方向に、景気が減退したら加熱する方向に」といったフィードバック的な手法を用いることでより良い経済状態を作り出すことはできる。お風呂に例えるならば「42度にする」といったことはできないが、「温水」を足したり「冷水」を足したりすることでちょうどいい温度にするといった感じであろうか。
市場機構による最適化を方法論とした市場主義経済や財政政策、金融政策といった経済の調整法が、恐慌を過去のものとし経済の変動幅をより小くすることに成功したことを考えれば、その力は極めて大きなものであると言わざるを得ない。経済学がもたらした変化は一日単位で日々を過ごしている我々には実感が湧きにくいかもしれないが、ここ半世紀の経済発展が経済学ぬきに語れないのも事実なのである。
経済の良し悪しとは何か
知人との議論や様々なエコノミストの主張を通して気付かされるのは、経済学に基づき主張をする人とそうでない人とでは「景気」に対する認識がまったく異なっているということである。私にはこのことが経済学者の主張が理解されずトンデモエコノミストの主張が氾濫する最大の原因なのではないかと思えてならない。東谷氏は次の文章により本書を結んでいる。
私たちが現在の長期停滞を本格的に抜け出す方途も、思いつきのような唯一の手段を見つけてひたすら邁進することではなく、いくつものバランスのよい結合を見出すことからもたらされるのではないだろうか。
この一見もっともらしく見えながら曖昧極まりない結論も、経済の良し悪しとは何であるのかを理解していないことから起こった誤解である。経済の良し悪しをきちんと枠組みとして捉えていれば、いんちきエコノミストから提案される処方箋の大部分が的外れであることが自然と見えてくる。
では、経済学者は「経済の良し悪し」をいったいどのように捉えているというのだろうか。
ときどき象牙の塔から出てくるマクロ経済学者の多くと同じく、ぼくも実際のビジネスサイクルはリアル・ビジネスサイクルじゃないと思っているし、一部の(いやほとんどの)不況は、全体としての総需要が落ち込むせいで起こるんだと考える。
山形浩生訳 ポール・クルーグマン著「クルーグマン教授の経済学入門」より
ここでクルーグマンが不況の原因として「総需要の落ち込み」を挙げている点に注意して欲しい。経済学に基づかない議論を行うエコノミスト達が、しばしば「日本がダメになったから」不況になったのだと主張しているのとは対照的である。とは言っても後者のような「生産性の向上」に類する概念を経済学者がないがしろにしているわけではない。クルーグマンは同書の別の箇所で「経済にとって大事なことというのは、(中略)3つしかない。生産性、所得配分、失業、これだけ」と生産性が極めて重要な概念であることをはっきりと述べている。経済学を学んだことがないものからすると、この二つの文章は矛盾に満ちたもののように映るかもしれないが、もちろんそうではない。
このことを理解するには、経済の良し悪しが「生産性」と「需給バランス」という二つの異なる要因から決まることを理解する必要がある。では、経済学者の思考を垣間見るために、経済の良し悪しを学者よろしく多少理屈っぽく考えてみることにしよう。
世の中を見渡したとき、ここ百年の間に我々はずいぶん豊かな生活が可能になったと感じることだろう。ほんの一世紀前には最低限の食い物すら満足に手にできず、飢饉が起こる度に大量の餓死者が出ていたなど想像もできない。
豊かさとは何であるかを考えたとき、哲学的に考えるならばいろいろあるだろうが、経済学では「自分の欲しいものをより多く手に入れることができる状態」であると考える。(現実的には人間は物欲の塊なので「より多くの物が手に入る状態」と同義であると考えても良い。また、愛や恋などといった所謂「お金で買えない価値」であっても「愛と一万円どちらを取るか、一億円ならどうか、一兆円なら……」と順次比較することで「お金で買える価値」と比較可能となる。それにそもそも愛や恋がコストと無縁などという戯言、現代人ならば誰も信じまい)
豊かさが定義ができたので、次は「より豊かになるにはどうしたらいいか」を考える。単純に考えたら「より多く生産すればいい」と思うかもしれないが、これだけでは不十分である。今まで一人一日一個作っていたものを二人で二個作ったところで、一人あたりでは以前と変わらない。そこで出てくるのが「生産性」という概念である*5。例えば、以前一人で一日一個作っていたものが生産性が上がり一人で二個作れるようになったならば、以前に比べ二倍の物を手にすることができる。
*5) 経済学では生産性というが、意味的には生産効率と同義。
国全体の豊かさは基本的にこの「生産性」のみで決まる。科学技術の発展、道路網など交通手段の拡大、より効率的な組織構造など知的資産の蓄積とそれを基盤とする物的資産の利用により生産性が高まり、我々は以前に比べより多くの物を手にすることができるようになったのである。これを理解することで、ひとつの重要な知見が導きだせる。前述の通り、生産性は知的資産によって規定される。そのため、短期的には物的資産の欠損や遊休によって生産性が落ち込むことがあっても、長期的には「決して減少することがない」のである。日本が長期停滞の状態に陥っているにも関わらず、ほぼ毎年GDPが増加していることを不思議に思っている人もいるかもしれないが、携帯電話の登場や情報機器の高性能・低価格化などからもわかるように生産性自体は年々着実に向上しているのである。
では、生産性が「決して減少することがない」にも関わらず、なぜ不況という現象が発生してしまうのだろうか。それは、長期的に見れば決して減少しないにしても、「短期的には物的資産の欠損や遊休によって生産性が落ち込む」ことがあるからである。
その最も大きな要因は、何らかの理由により需要と供給のバランスがくずれてしまうことにある*6。クルーグマンが言うように需要が落ち込み、供給を下回った状況を想像してみてほしい。企業は、その時代の生産性にて可能な量・質の製品を製造し販売する。しかし、いくら製品を作ろうとも需要がないのでは、その部分がボトルネックとなってしまい商品を売り尽くすことができない。売上の低下は収益の低下に繋がり、収益の低下は賃金の低下に繋がる。そして、賃金の低下がさらに需要を押し下げてしまうことになる。こうしてさらに深刻化した需要の低下は、同じ経路を辿り生産量を引き下げることになる。
逆に太平洋戦後直後やオイルショック時のように供給が制限された場合はどうだろうか。この場合には、供給不足によって起こった商品の値上がりが需要の低下を引き起こすことになる。すなわち、需要と供給のどちらかが低下すると、その部分がボトルネックとなってしまい、経済は潜在的な能力を下回った状態でしか稼動ができなくなってしまう。
我々の生活が昔の人びとに比べずいぶん豊かになっているにも関わらず、GDPがマイナスになるような経済の停滞すなわち不況という悲劇に見舞われるのは、この需給ギャップによる経済活動の停滞という極めて目に見えにくい問題が原因となっているのである。
*6) 景気が悪い理由は需要が低下していることだが、景気が悪くなった(=需要が低下した)理由は必ずしもひとつではない。戦争による国土の荒廃、石油価格の上昇、増税、金融政策の失敗などのように分かりやすいものもあれば、景気の過熱により一時的に消費を遥かに上回る生産が行われてしまうことが原因になることもある。
構造改革では景気が回復できない理由
前章の議論から経済の良し悪しは、「長期的には、決して減少することがない」ことが判明したが、需給バランスの議論からはどのような知見が得られるのだろうか。
それは「生産性がいくら上がっても、需給ギャップによるロスがなくなるわけではない」ということである。需給ギャップによる損失は、絶対水準の低下ではなく稼働率の低下(相対的な水準の低下)である。今まで月産100個の製品を生産する能力がある工場が、需要不足により80個しか作っていなかったとする。だがこの状況で月産200個の製品を作れるように生産性を改善したところで(値段が半分になって倍売れるようになったと考えても)160個しか売ることはできない。確かに、生産性の向上分は経済は良くなっているものの、稼働率の低下から起こる損失が減るわけではない。実際にはそれどころか、生産性の向上によって供給サイドだけが活発化し、以前よりも需給ギャップが拡大してしまうことにもなりかねない。
構造改革とは、前者の「生産性」を向上させる政策である。もし、現在が生産性の伸びが極めて低下したことが原因で経済が停滞しているならば、構造改革で景気回復という主張も納得がいく。だが、1998年、2001年には経済成長率マイナスすら記録しているし、立場的に日本とほぼ同レベルの経済水準にあるはずのアメリカはたしかに成長の伸びは鈍化しているとはいえ、日本より遥かにましな経済成長率を達成している。このことを考えると、経済低迷の原因を生産性の伸び率低下に求めるのは難しい。
また、経済学の観点から見れば、生産性の伸び率の低下が経済低迷の原因だとすると、現在の状況は古典経済学が考えていたような完全雇用状態であるということになる。だがこの状況では「就職したい人は適切な賃金さえ要求すればいつでも就職でき」、「インフレ・デフレは経済に影響を与えない」はずである。このことを考えれば、現在の状況が完全雇用状態であるなどということはとても考えられない。
とはいえ、構造改革として挙げられる「行政改革」や「金融改革」などといった施策は、国家を長期的に成長させるためには必要不可欠な要素である。日本の長期的な行き先を憂いている政治家の皆様なら、今の幸福を捨ててでも、未来を良くすべきであると思うのも理解できなくはない。
だが、ケインズが言うように「我々は長期的には皆死んでいる」のだ。少なくとも今食うのにすら困っている人がいるなら、それを解決するのが優先であろう。しかも、構造改革は景気回復と二律背反ではない*7。構造改革を行いながら、景気を回復させることには何ら問題がない。しかし、経済が悪化し続けているにも関わらず構造改革だけを断行するならば、クルーグマンの言うように「小泉政権の絶対的スローガンは“改革か破滅か”である。しかし、実際の結果が“改革したら破滅”になってしまう可能性は危険なほど高い」のである。
*7) 世の中ではなぜかリフレ派が構造改革に反対していると思っている人がいるようだが、それは大きな勘違いである。リフレ派はどっちもやれと言っているのである。
景気を回復させるには
このように言うと驚く人もいるかもいるかもしれないが、実のところ景気を回復させるための方法というのは、たった二つしか存在しない。「財政政策」と「金融政策」である*8。
前述のように、(不況の起因は別としても)不況が続く原因は「需要の低下」にある。で、あるならば対策は「需要の回復」を行うだけである。需要は、個別に見ると日々我々が行っている「消費」であったり、企業が未来の成長のために行う「投資」であったりする。もし政府がこれらの要素を操作できるのであれば、景気を回復させることが可能ということになる。
*8) これを知ってると、なんで経済論戦がこんなに混乱しているのか不思議でならなくなる。
まずは、「財政政策」。小渕政権時には極めてもてはやされたにも関わらず、最近不人気な財政政策であるが、これは国民に代わって政府が投資を行うという政策である(減税も政府のお金を民間に流して消費を増やすという意味で財政政策の一種と考えられる)。財政政策が国民の多くに人気がない理由は「無駄な公共事業が多い」という一点につきると思うが、実は経済を回復させるという意味で言えば用途がどうだろうと関係はない。例えば、政府が金を10兆円土建屋さんに注ぎ込むと、土建屋さんの収益は改善する。だが、これで終りではない。収益の改善により今度は土建屋が新しい投資を行うかもしれないし、給料が増加して従業員が消費を増やすかもしれない。こうして起こった需要の増加が他の産業の収益を改善させ結果的に「当初注ぎ込んだお金以上に需要を増やす」ことになる。
これが本書にも出てくる「乗数効果」であり、経済学者の試算によれば最初に注ぎ込んだ金額の10倍程度の効果が出るため、赤字国債を発行しても十分元が取れるとされる。小渕政権時の大規模な財政政策により、一時的とはいえ景気が改善したことを思い出せば、財政政策に効果があることに自体には疑問の余地はない。
だが、この財政政策という20世紀前半から存在する古き良き経済政策は、現在においては当の経済学者自身からも人気がないのである。理由は、本書にも書かれている通りで、「たとえ財政政策を行っても将来増税が待っているならば、今の消費を増やさない方が合理的選択となる」という逆ケインズ効果や、現在の日本のように深刻なデフレ期待がある場合には注ぎ込んだお金がほぼ貯蓄に回るという打ち消し効果が現れるなどの理由により(少なくと今の日本では)極めて低い乗数効果しか現れないことが明らかになってきたからである。内閣府の政策研究官 原田泰氏の試算によれば、ここ十年間に行われた日本の財政政策の乗数は0.5~1.5程度であり、とても10倍などという効果は出ないとのことである。
有効性に疑問の出てきた財政政策に代わり現れてきたマクロ経済学者おすすめの秘密アイテム、それが「金融政策」である。
金融政策は「国家はお金の価値を操作できる」という特権を駆使することで金利を変え投資量を変化させる政策である*9。我々はお金の価値が変わらないと考えがちであるが、大学で経済学の授業を受けるとまず教えられるのは「お金の価値は変化する」ということである。
ハイパーインフレが起こったことでお金が恐ろしい勢いで紙切れ同然になっていく映像を見たことのある人もいるかもしれない。日本のようなまっとうな国家ではそのようなことはなかなか起きないが、お金を銀行に預ければ金利がつくし、インフレやデフレが購買力に関わってくることくらいは理解できるだろう。インフレやデフレは、物価価格の変化という側面から説明されることが多いが、物価が上がれば買える物が少なくなる、すなわち「お金の価値が下がる」わけだから、それはお金の価値の変化と言い換えることができる。
通常、金融政策は政府の一機関である中央銀行により行われる(日本では日本銀行がそれにあたる)。中央銀行は、お札の印刷と金融機関へのお金の貸し出しを行う機関である。そのため、作ろうと思えばいくらでも「本物の」お金を作ることができる。お金の価値を操作する方法はいくつかあり、有名なのは「公定歩合の変更」であろう。これは、お金の入り口である各銀行への貸し出し金利を変更することでベースとなる価値を上げ下げする政策である。もうひとつは、量的緩和というもので、これは市場原理に基づきお金の供給量を増やすことで価値を下げる(=金利を下げる)という手法である。
中央銀行は、景気が悪い時には金利を下げ、景気過熱時には金利を上げることで投資を制御し経済の安定的な運営を行うのである。金融政策は、野口旭の言うように現在世界的に最も主流な経済安定化手法となっている。
*9) 実は為替もこの金融政策により決まるため、為替政策と呼ばれるものは金融政策の裏側のような存在でしかない。為替レートは、二国間のマネタリーベース(お金の量)の比で決まる。財務省が度々介入するにも関わらず数日で元のレートに戻ってしまうのは、これが理由である。
ただ、この金融政策も磐石というわけではない。金利の変化が、経済に実に大きな影響を与えることは過去のデータからわかっているが、我々庶民には直感的でないこともありなかなか理解されない。庶民に理解されないだけならいいが、残念ながら政治家、そして当の日本銀行の人びとにも理解されにくいようである。
問題は、それだけではない。本書でも小宮隆太郎氏の言を引用し金融政策に対する疑惑を提示しているが、「深刻な不況期には効果が弱まる」という問題は経済学者の一致した見解であるし、開放経済下ではその有効性が低下するのも確かである。また、クルーグマンの言う「流動性の罠」による金融政策無効論は、日本の置かれている深刻なデフレ不況時には金融政策の効果が限定的であることを示している。
それでも、インフレ・ターゲットで景気は回復する
財政政策もダメ、金融政策もダメ……では、どうすればいいのか。ひとつは諦めることである。だが、多くの人はこの結論に納得すまい。他に打つ手はないのか。
もちろん、ある。もう一度よく読んで欲しいのだが、財政政策も金融政策も「まったく効かない」とは書いていない。確かに効果は通常時ほど大きくはないが効かないわけではないのだ。もし景気回復を諦めないのであれば、我々はその手段として「財政政策」と「金融政策」に頼るしかない。スティグリッツ経済学にも次のように書いてある。
(金融政策が深刻な不況期には効果が弱まるということに関して)しかしながら、金融政策の擁護者たちは、重要なのは金融政策に何らかの効果があるということである、と主張している。彼らにとっては、(マネーサプライの増加がもたらす)効果が弱いということは、金融当局はより積極的な行動をとるべきである、ということを意味しているにすぎない。*10
ジョセフ・E・スティグリッツ著 藪下史郎など訳「マクロ経済学第2版」より
*10) 研究・調査が進んだ結果、現在ではこの「金融政策の擁護者」の立場が大勢となっている。この共通認識の確立に日本の長期停滞がおおいに影響を与えたことは言うまでもない。
ただ、ここで次の二点を考慮する必要がある。
景気が回復するまで政策を持続できるか
弱まった政策効果を回復させる手段はないか
前者の「景気が回復するまで政策を持続できるか」という点であるが、ただでさえ効果が限定的なのだから、需給バランスがきちんととれるまでずっと政策を継続できることが求められるということである。だが、ここで財政政策は問題となる。現在の日本の状況を見ればわかるように、大規模な財政政策を行うには国債を発行することで費用を賄う必要がある。だが、その金額は日本銀行やIMFなどの試算で25兆円、米FRBのバーナンキの試算では130兆円ほどにもなるとも言われている。ただでさえ厳しい財政状況の中、多額の資金を捻出し、それでもなお景気が回復しないようであればさらに国債を発行し続けなければならないというのは政治的にも経済的にもあまり考えたくない状況であろう。それに対して金融政策には、このような制限はない。お金の価値を下げたければ、好きなだけお札を刷ればよいし、インフレ率が高くなりすぎたら銀行への貸し出し金利を引き上げることで、いくらでもインフレ率を下げることができる。
それでは、後者の「弱まった政策効果を回復させる手段はないか」という点を考えてみよう。たしかに金融政策をすごい規模で行い続ければいつかはインフレになり投資が促進され景気は回復するだろう。だが、もし弱まった政策効果を高めることができるのであればそれに越したことはない。そこで出てくるのがインフレ目標策*11である。
現在、日本で金融政策が効きにくい最大の理由は、金利の0%制約による流動性の罠的状況と強力なデフレ期待(今後、デフレが続くだろうという予想)が存在することにある。例えば、来年5%のデフレになると思うならば、5%に満たない利益しか得られないような投資を行うよりも現金を持つ方がお得ということになる(リスクを考えるならば、もっと大きい利益でも投資を控えるだろう)。このようにインフレ(デフレ)率を考慮した金利を「実質金利」と言うが、日銀の貸し出し金利がすでに0%になってしまっている今の状況ではこれ以上の引き下げができないため、デフレ期待の分だけ実質金利は高くなる。
インフレ目標策とは人びとに将来インフレになると予測させることでこの実質金利を引き下げ消費や投資を促進する政策である。もし明日ハイパーインフレになるならば、皆今日中にお金を使い切るだろう。これは極端だが、方法論としては同じことである。しかも、本当にインフレ率が高くなってしまうようであれば、逆に金融引き締めを行ってインフレ率はいくらでも下げることができる。東谷氏は「インフレ目標に前例がない」ことを非常に気にしておられるようだが、こと引き締めに関してはその実績に事欠かない。
インフレ目標策を用いれば、このようなフィードバック的手法によりインフレ率を数%というマイルドな水準に留めることが可能になる(岩田喜久男などが挙げる3%程度のインフレ率と言うのは、過去のデータから見て最も安定的な経済成長が可能になるインフレ率でもある)。
*11) インフレ目標策に関してはリフレFAQ「余は如何にして利富禮主義者となりし乎」を参考のこと
このように論理的に有効性が明らかに思えてもなお、インフレ目標策は東谷氏の言うように「理論的にも実証的にも保証のない政策」なのだろうか。
少なくとも理論的に保証があるのは確実だ。なんせ論文だけ書いて暮らしているマクロ経済学者達のお墨付きをもらっているのだ。また、東谷氏の引用する小宮隆太郎氏の「深刻な不況期には効果が弱まる」という批判は、そもそもインフレ目標策が「そのような状況でも金融政策を有効にする」ために提案されたことを考えれば的外れと言わざるを得ない。
では実証面ではどうだろうか。たしかにこの面ではインフレ目標策が頼りないのも確かである。ニュージーランドでの成功例や、恐慌時の研究を通して裏付けは学会的には十分あるかもしれないが、ジャーナリストでも納得できるような分かりやすい話ではない。ただ、ここ半世紀は知っての通りインフレの時代であって、デフレになった国自体がほとんどない以上、仕方のないところもある。
しかし、「インフレ目標」のリスクを判断することで、実施する価値があるかどうかは十分に判断できる。前述の通り、インフレ目標によって高率のインフレになることは有り得ない。それならば、インフレ目標が失敗と判断される状況では何が起こるのだろうか。それは「何も起こらない」ということである。だが、これすらもバーナンキの背理法*12を使えば即座に否定できる。
すなわち、インフレ目標策を適切に運用すれば日本は「必ず」不況から抜け出すことができるのである。
*12) 「中央銀行が国債を含む資産を買いつづけてもインフレにならない(=お金の価値が下落しない)」と仮定する。すると、中央銀行は世界中の資産を買い占めることが可能になり、政府は無税で国家を運営できるようになる。こんなことはありえないので、最初の命題は否定される。すなわち、「中央銀行が国債を含む資産を買いつづければ、必ずインフレになる」のである。
エコノミストの評価は経済学で
東谷氏の最大の問題は、科学の力、ひいては学問の力を理解していないことにある。たしかに、ひとりひとりを見れば現実を知らない議論をする学者も少なくない。しかし、総体としての学問は、数百年という期間に渡ってデータを調べ、理論化し、検証するという作業の積み重ねを経て集積されたものである。まさに人類が歴史から手に入れた知的資産そのものなのである。
学問が人類の知的資産であるということは、学問を用いても理解できない物事は誰も確かなことを知らないということを意味する。もし誰かが学問で説明できないことを説明できたとしても、それは単なる思いつきか勘違いである可能性が高い。まれに真実だったりすることもあるが、それは理論化もなされていなければ、検証もすんでいない段階の思考である。他人を十分説得できるほどの信頼性をまだ獲得できていないはずのものである(信じるのは勝手だが)。
東谷氏は、エコノミストの格付けをもくろんだわけだが、エコノミストは評論家である前に経済の専門家であるはずである。当然、その評価は如何に適切な経済の知識、見識を持っているかに寄らねばならない。
では、適切な経済の知識・見識とは何であろうか。当然、それは人類の知的資産たる経済学である。物理学に基づかない議論をするサイエンティストをあなたは信用するだろうか。経済学に基づかない議論を行うエコノミストがいる現状の非常識に気付いてこそ、はじめて信頼に値する格付けが可能になるのである。
おわりに
長々と批判を行ってしまったが、前述の通りこの「エコノミストは信用できるか」という本は良書である。その時々でなされるエコノミストの言説を保存・整理するという作業は、本職の経済学者ではできないジャーナリストならではの仕事であり、賞賛されてしかるべきであるように思う。私がこの文章を書こうと思ったのも、本書がトンデモ本ではなかったからである。トンデモ本であればたとえ内容を信じてしまっても、読解力のない読者の責任であろう。しかし、本書のように証拠資料を元にし、学会では通用しなくともジャーナリストとしては適切な文章で書かれては、真相を求め知識を探求する人の妨げになるかもしれない。
すでに日本は失われた十年どころではない長期停滞のただ中にいる。これ以上、インフレ目標策の採用が先延ばしにされ不適切な経済運営が行われるなどということがあってはならない。日本銀行がその実行を躊躇しつづける以上、我々国民ひとりひとりが経済学の正しい知識を身に付け政府に圧力をかけつづけることが重要である。(消極的だと思うかもしれないが、これくらいしか方法が思いつかないのである)
政府が経済学に基いた合理的な経済運営を行うことこそ、真の構造改革である。一日も早くそのような日が来ることを私は願ってやまない。
2004/01/10 英-Ran
--------------------------------------------------------------------------------
質問とその回答
Q. この本を良書だと言っていますが、最後にはこの本が誤解を生みかねない危険性にふれています。こういう危険な本を「良書」と呼べるのでしょうか。
A. 何をもって「良書」と呼ぶかは人によっていろいろあるかと思いますが、私は著者の東谷氏があくまでジャーナリストであるという点を考慮しています。ジャーナリストの仕事は、真実を追うことと思われがちですがジャーナリストの名著と呼ばれるものを何冊か読む限りでは、重要なのは「人びとが思っていることをデータで裏付け、説得力のある形で提示すること」にあるのではないかと感じています(すなわち、真実は説得力を得るために必要ではあるけど必須というわけではない)。真実を追い求めるのは学者や警察の仕事であるわけですから、そもそも真実を追い求めることを目的とするならジャーナリストはほとんど失業してしまいます。
著者の東谷氏が本書で追い求めた点は「エコノミストの奴らってのはみんな不誠実なんだぜ」という多くの人が薄々感じていたことを説得力ある形で提示することだったのではないかと思います(だからこそ、どのエコノミストの主張にも反対の立場をとる)。そう考えると、本書に掲載されているエコノミストたちの発言は、十分に説得力を持つ形で提示されているように思います。
また、たしかに著者の主観が反映されている部分も多いとはいえ、その論法の多くは「Aの主張に対してBはこのように反論しているから、Aには疑念がある」というものであり、東谷氏自身が必ずしも間違った主張をしているわけではないことにも注意が必要です。
それ以上に、エコノミストの発言を追うことで問題あるエコノミストを炙り出すという手法は、(今までなかったのが不思議ではあるけれど)東谷氏が最初に行ったのであり、その開拓者としての評価は十分可能であるかと思います。
マルクスの資本論が危険なように、この本は良書だからこそ危険なのです。人の心を引きつけない本は、そもそも読まれないので、たとえ間違っていてもその主張が広まる心配はない。リフレ派は100年デフレやら国債暴落やらも相手にしていますが、ああいった類の本は「ノストラダムスの大予言」がそうであったように、実のところみんなそんなに信じてるわけありません(本当に信じているのなら、今頃民族大移動が起こっているだろう)。本当に危険なのは、この本のように一抹の真実(と根本的な誤解)が含まれている本なのだと私は考えます。
更新履歴
[2004/01/12]
タイトルが「エコノミストの誤謬」となっていましたが、書き間違いでした。正しくは上記の通り「ジャーナリストの誤謬」です。
「エコノミストは『主張の一貫性』で評価されるべきか」の章にて「ある経済学者とは、野口旭のことであると思われる」と書きましたが、実際には「経済学者たちの闘い」からの引用であることが判明しましたので修正を行いました。
[2004/01/13]
「景気を回復させるには」の章で、財政政策を19世紀前半と書いていましたが、正しくは20世紀前半です……ここは割と念入りに調べたはずなんだけどなぁ。最初1900年代前半と書いてあったのを校正中に間違えて修正してしまったらしい。
[2004/01/15]
「はじめに」にて「著者の東谷氏は十年にもわたりエコノミストの言説を追う中で、論点となっているのが『構造改革 VS インフレ目標』であることをきちんと見抜いている」と書きましたが、たしかに金融政策とインフレ目標にページを大きく割いてはいるものの対立軸を見抜いているというのはいいすぎのようにも感じられるので「『インフレ目標』が大きな争点のひとつになっていることをきちんと見抜いている」という文章に修正しました。
目次
はじめに
エコノミストは「主張の一貫性」で評価されるべきか
経済学に国境はない
経済学は経済を予測できるか
経済学は役に立たないのか
経済の良し悪しとは何か
構造改革では景気が回復できない理由
景気を回復させるには
それでも、インフレ・ターゲットで景気は回復する
エコノミストの評価は経済学で
おわりに
--------------------------------------------------------------------------------
質問とその回答
更新履歴
Top
Copyright c 2004 英-Ran
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: