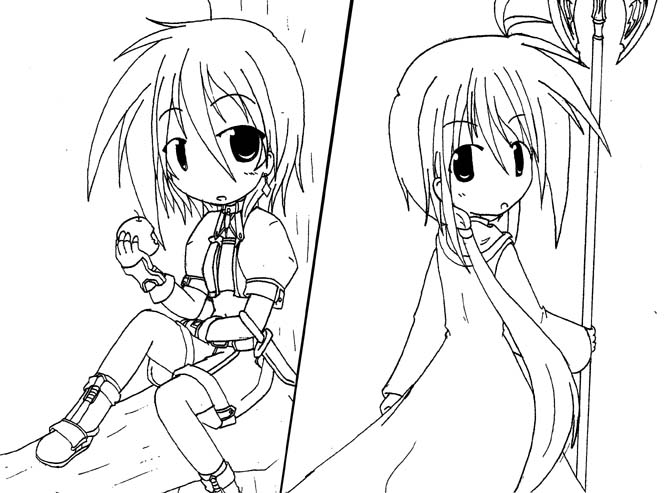-ある日の風景-
1:ティール編
「―滾るは心――燃えるは魂――我が力、内なる灯火と共に――」
意識を集中し、魂の炎を解放する。
慣れ親しんだ炎の力……しかし、今発現するそれは、いつもとは少し違う
「―サイレント・ブレイブ―」
彼女のその力を見慣れた者なら、今ここに拡がっている光景に違和感を感じるだろう。
いつもならば近寄ることも許さないかのように激しく顕現する炎が、身体の表面を僅かに覆う程度の光まで弱まっている。
……が、これは決して弱体化では無い。
外に放出される炎の力を体内に抑え、その分身体強化の効果に出力を割く。
これをすれば、炎による属性的な攻撃は弱まり、ほとんど意味を成さなくなるが――それは、最も単純明快な身体強化。
純粋に戦闘力を上げる、『ブレイブハート』の別形態である。
「……その能力って、使いにくくない?」
ひとつの会話が始まるのに、前振りが必要とは限らない。
確かに何らかの話題の種が転がっていなければ起こり得ない事も多いが、誰かが口を開けば、それ自体が発端となってそのまま始まるのが、会話というものである。
「いきなりなに?」
だからといってどうした、ということもない。
ただ、それまで風と草のざわめきのみの静寂に包まれていた街道外れの草原に、人の声が混ざり始めた……それだけのことである。
「感情をそのまま炎と力に変えるのが『ブレイブハート』 逆に言えば、テンションが低いと全然意味ない能力じゃん?」
「…………」
手近にあった木の枝に腰掛け、リンゴをかじりながらそう口にする少女――リーゼ。
その声を耳にして、目を閉じて集中していたらしいティールは構えを解き、リーゼの方へと視線を向ける。
「……ま、確かにね。ひどい時だと発動すら出来ないこともあるし」
-ブレイブハート-
とある異世界の民が持つ、『魂』能力の元に発現する炎の力。
その効果は、術者の身体を炎の鎧で包み込み、かつ身体能力を急上昇させるというもの。
そして最大の特徴は、二人の会話の通り、術者の精神状態が大きく影響するというところだろう。
「でも、この能力はまぎれもなく私の力のひとつ……それに逆に言えば、心持ち次第では最強の能力にもなりうるからね」
「……最強、ね」
確かに、テンションを高めればそれだけ効果も増すと言うのなら、それだけの力はひねり出せるだろう。
……だが、リーゼはそんなに直接的な『力』ではなく、また別のところに食いついていた。
「あんたが自分の事で『最強』なんて言葉使うとはね」
そう言いながら、明日は雨か? とばかりに空を見上げるポーズを取るリーゼ。
ティールが最強という言葉をあまり使おうとしないのは、彼女に近しい者なら誰でも知っていること。
彼女にとっての『最強』とは一体どういうものなのか……恐らく、彼女の師であり家族でもあった、という『英雄』のことだろう、と多くの者は推測している。
とはいえ、その英雄とやらは彼女が元々いた世界の住人であり、この世界にいる限り会えるようなことはまずないので、その正体もまた、推測に留まっているのだが。
「関係ないよ。 たとえ能力がそうであったとしても、それを扱う私自身が力をつけなきゃ振り回されるだけ。 だからこそこうして――」
そう口にした刹那、彼女自身を包みこむように青白い炎が展開して、次の一瞬には収まりを見せる。
「――少しでも上手く扱うために、修行してるんだから」
「…………」
全てを焼き尽くすような激しさと、ただ風にゆらめくような静けさを併せ持った魂の炎。
『魂』能力とは、文字通り魂の具現。
単純な性質だけを言うのなら単なる身体強化能力に+α程度のモノなのだが――その効果は、主として術者の精神が投影されるもの。
静と動が混在するその炎は、いったい何を意味しているのだろうか。
「……でもティール。 それって、自分の『心』を上手く扱おうとしてるってことじゃないの?」
「ん?」
「安定した力を得ようと思うなら、自分自身の感情を制御する必要があるわけでしょ? ……まぁ、それはどんなコトにも言えることだと思うけど」
リーゼのエレメンタルウェポン『紫電の双剣』もまた精神の具現であり、ブレイブハートほど極端では無いが、ある程度は使い手の精神状態に左右される。
……しかし、その理屈はおおよそあらゆることに対して当てはめられるもので、精神的に揺れている状態では、熟練の戦士と言えども手元が狂うこともあるし、魔術師であっても、普段当たり前に使えている魔法が、うまく使えなくなったりすることもある。
だからこそ、戦場においては心――感情の制御は重要な要素ではある。
「アンタは人の『心』に特にこだわる性格だよね。 付き合いはまだそんなに長く無いけど、そのくらいは分かるよ」
「……」
「表情とか言動から、相手の性格や表層的な感情を読み取る才能――それも、その性格が影響してるんじゃ?」
ティールは、何かと他者の精神的に弱い部分と強い部分を察し、その場で何か一言を投げかける、という行動に出る事が今までに何度もあった。
……また余談ではあるが、それなりに長い付き合いである相手に対しては、理解も深まっているせいか少し深い部分まで読めてしまうときがあるという。
「ま、それはいいんだけど。 他人の心には救い手を出しておきながら、自分の心は道具みたいに扱ってる気がしてね」
「……リーゼ、いくらなんでも考えすぎ」
と、相手のセリフが一区切りついたところで、少し呆れたような顔を見せながら、そう口にするティール。
リーゼは自分の意見が切り落とされたことに特に気にした様子も無く、”そう?”と言い、また手元のリンゴにかじりついた。
「確かにこの能力でも安定して戦えるのが理想だし、私自身心を乱さないようにしているのも確かだけど……それは誰でも同じこと」
「ふぅん?」
「私は戦場と日常を区別しているだけ。 戦いの場では何よりも冷静に、けど、日々の生活の中じゃ戦場ほどに心を抑える必要は無いよ」
日常での心の抑制――要するにそれは社交的な分別程度で、怒る時は怒ればいいし、笑いたいなら笑えばいい。
ただ戦場においての感情の振れは、場合によっては致命的にもなりうる。
それなりに戦い慣れた者であれば、戦場におけるある程度の感情の抑制は身につくものだ。
……仲間の死や裏切りなどに対する感情では、その抑制も限界はあるかもしれないが。
「でも、『心』を道具にしなければならない状況がありえるのは確かだし、そう思った事があるのも確かだよ」
「へぇ、珍しいこと言うね」
「楽しみ・喜び・信頼――心を高ぶらせる感情は力を産み、悲しみ、動揺、後悔――落ち込ませる感情は力を奪う。そんな能力なのは分かってたから……最初の頃は、意図的に『心』を高ぶらせる事が出来たら、どんなに楽だろうと考えてた」
「ま、気持ちは分かるけどね。 心がそのまま戦闘力に影響するってんじゃね」
「……一番力が出せるのは『怒り』だけど、それで産み出された炎は私自身も焼き尽くす諸刃の剣。 正直、コレだけは避けたいかな」
……何か月か前にあった、イリスを巡っての戦いの中――ティールは、憎悪の中で炎を使っていた。
全てを蹂躙する、攻撃的な感情の爆発。
それはどちらかと言うならば暴走に近く、技を放った直後に自分自身が倒れてしまっていた。
――それを思い出し、少し苦笑いをみせるティール。
彼女の中では、苦い思い出の一つなのだろう。
「いっつも冷めてるみたいに思ってたけど、結構色々考えてたんだね」
「…………冷めてる、か。 まぁ、人にはない経験をしてきたってのは、あるかもしれないけど」
「……暗い話っぽいね」
「興味ある?」
「あるけど無理には聞かないよ。 心の闇ってヤツでしょ?」
「ま、ね。 聞くも語るも涙の話」
そう口にしながら、お互いに取り繕うように笑顔を見せる。
興味はあれども、相手の考えを察し、あえて断る――これもまた、日常における感情の抑制。
「……色々と経験をすれば、ボクも強くなれるのかな」
リーゼはそう口にした後にリンゴの最後のひとカケラを食べ、そのまま芯を投げ捨てる。
その瞬間には、直前には見えなかった複雑な表情が浮かび上がっていたが、空を見上げるように上に向けていたために、ティールの目にその顔が映る事は無かった。
「辛いコトを乗り越えて得る強さは、確かにあると思う。 ……けど、心に闇を背負う強さは、悲しいよ」
精神的な強さは、身体的な力のように直接鍛える事は難しい。
その瞬間に彼女がどんな顔をしていたのか……ティールは、漠然とだが察していた。
「……言うね、ボクより年下のクセに」
「人生の密度なら負けてないつもりだよ」
しかし、最後に二人が見せた表情は……
どこか楽しそうな、友へと捧げる笑顔だった。
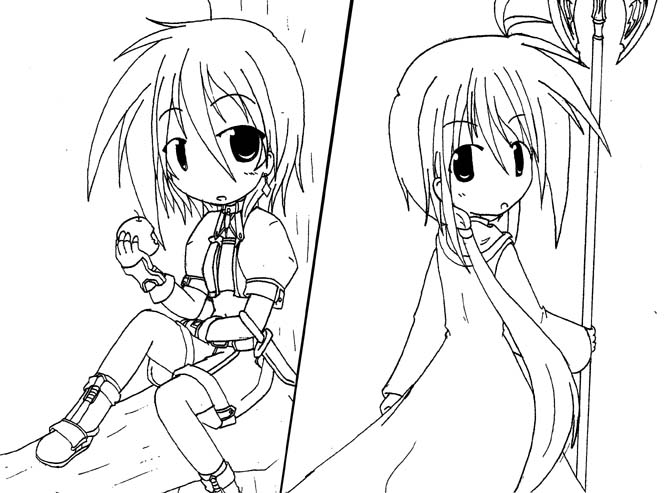
最終更新:2008年02月08日 22:32